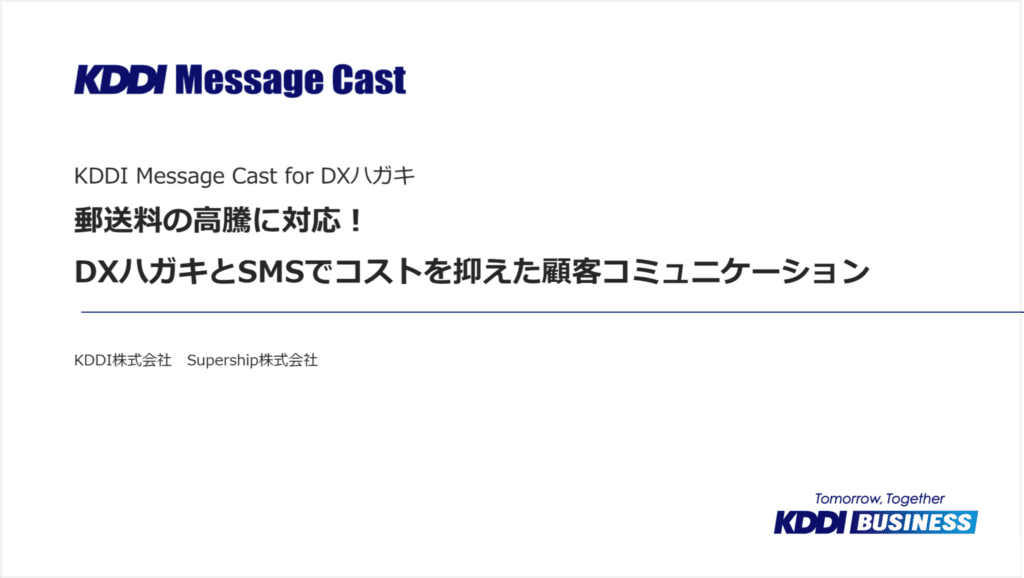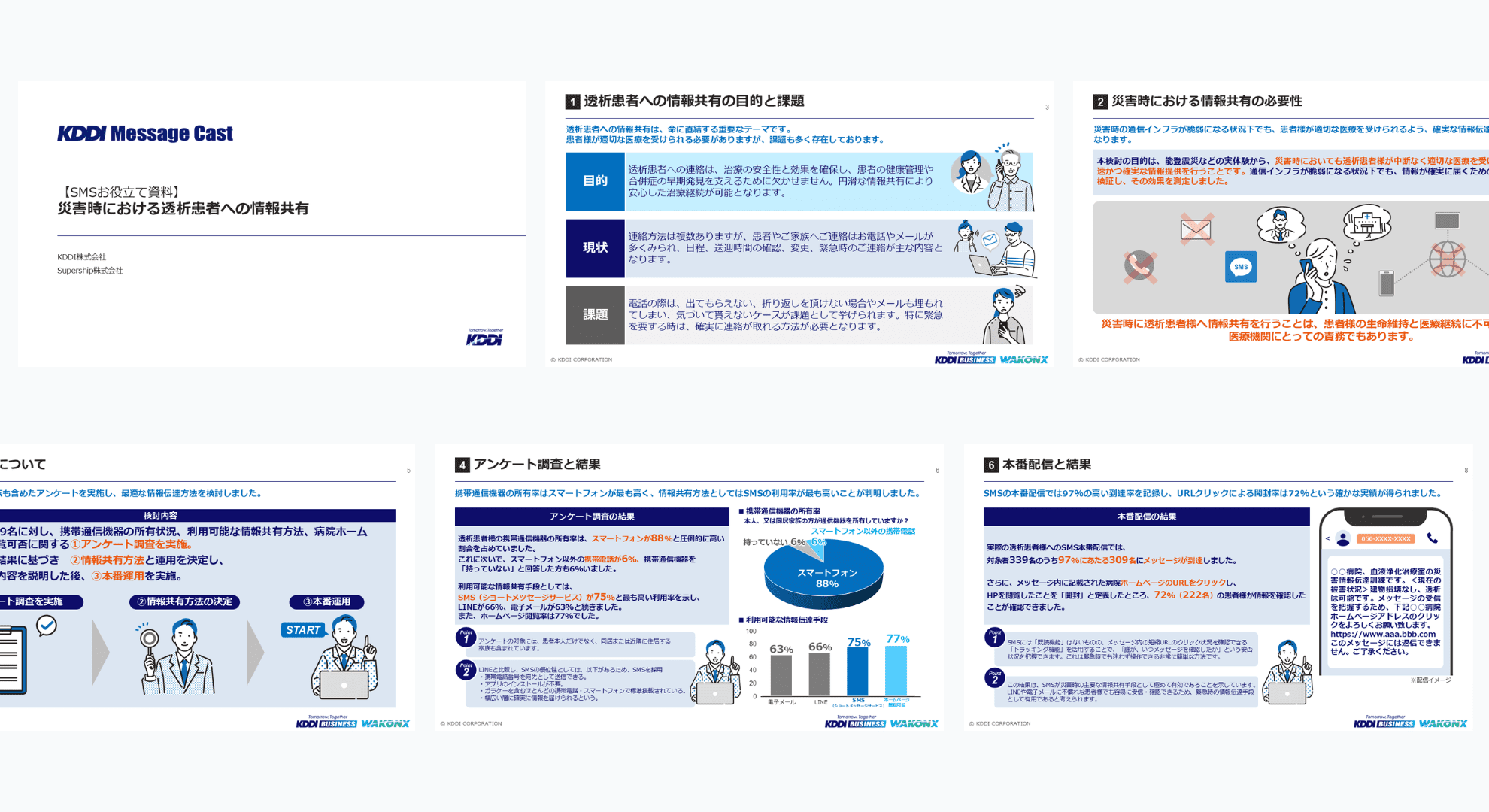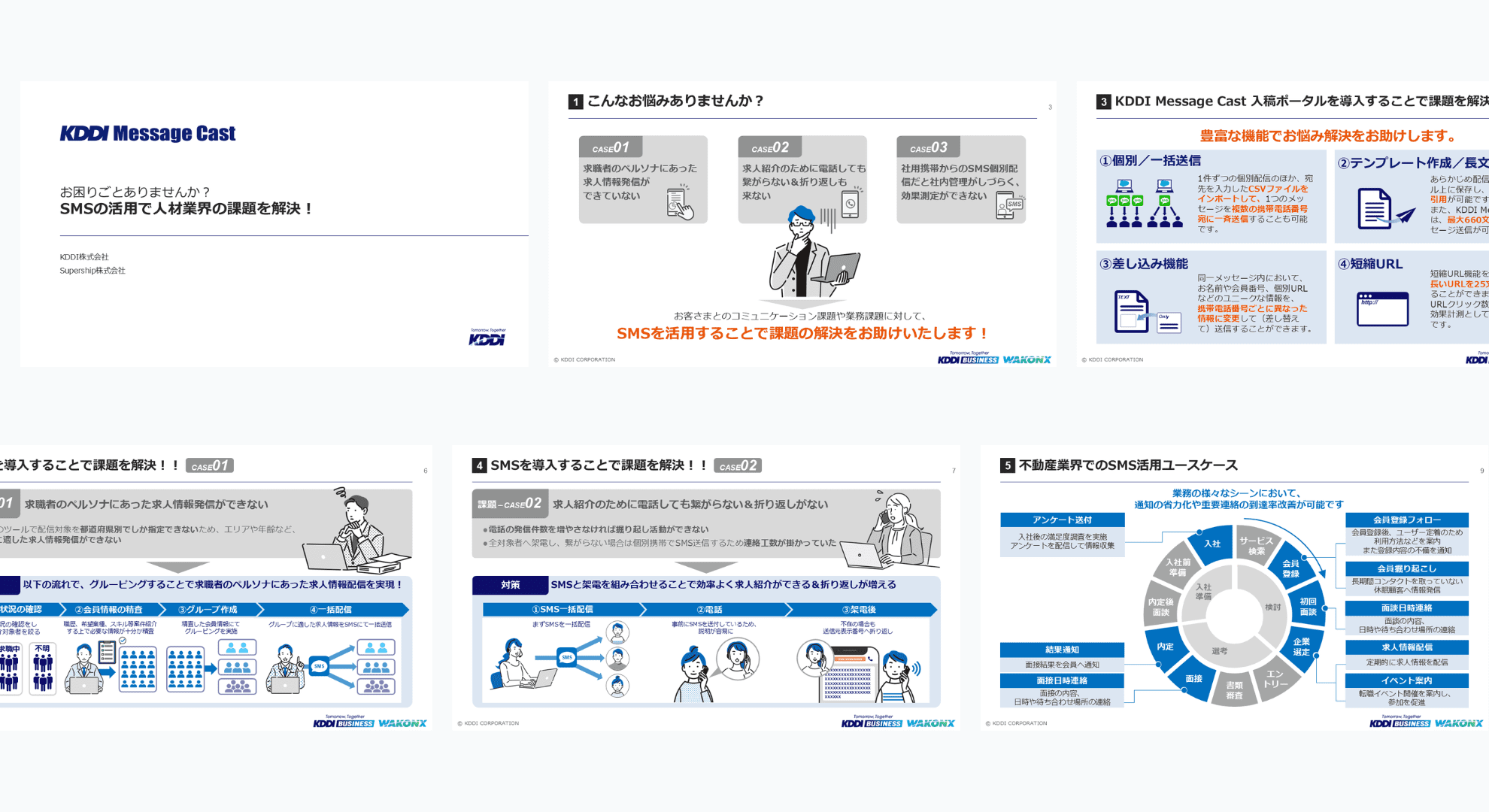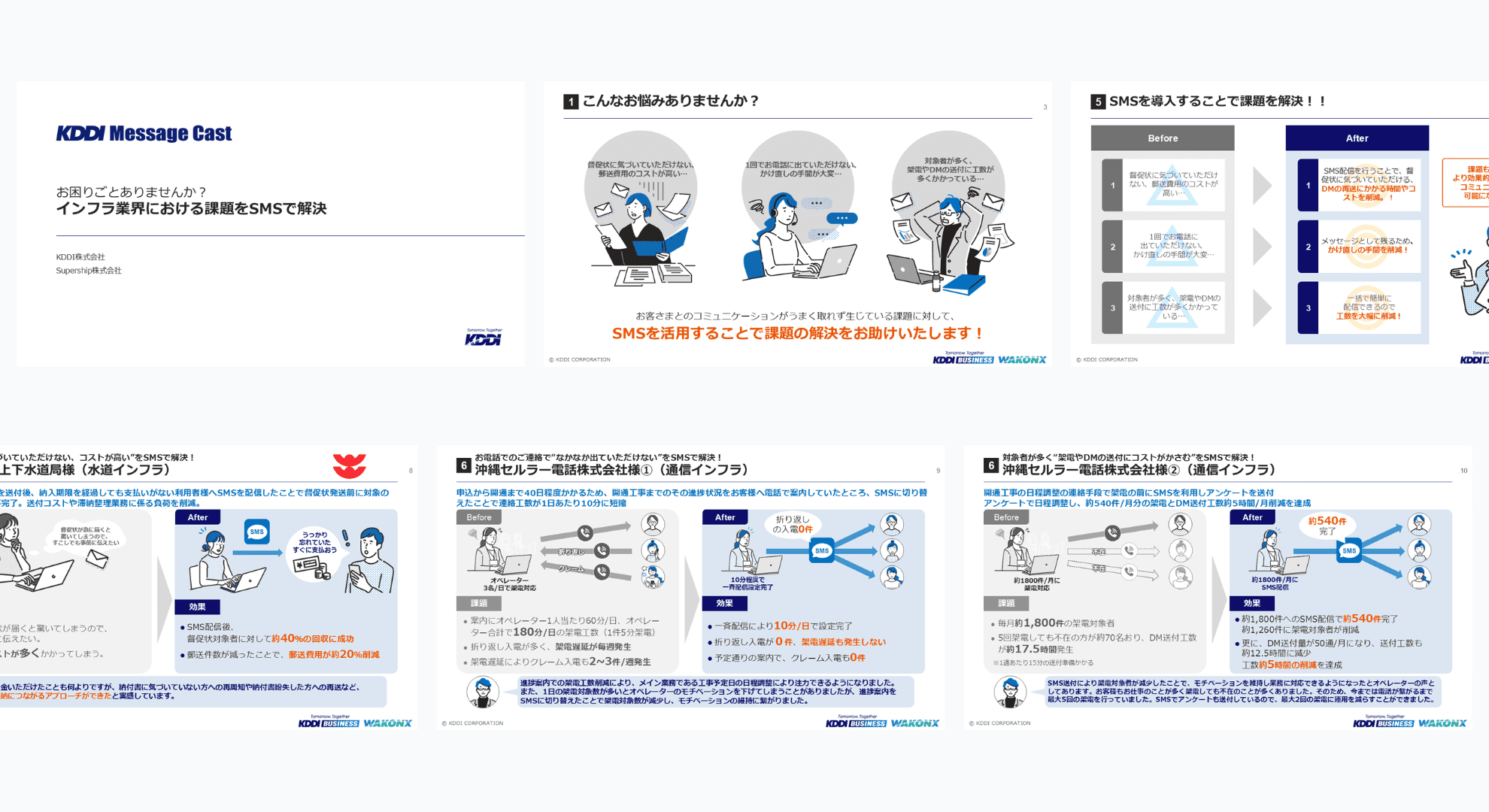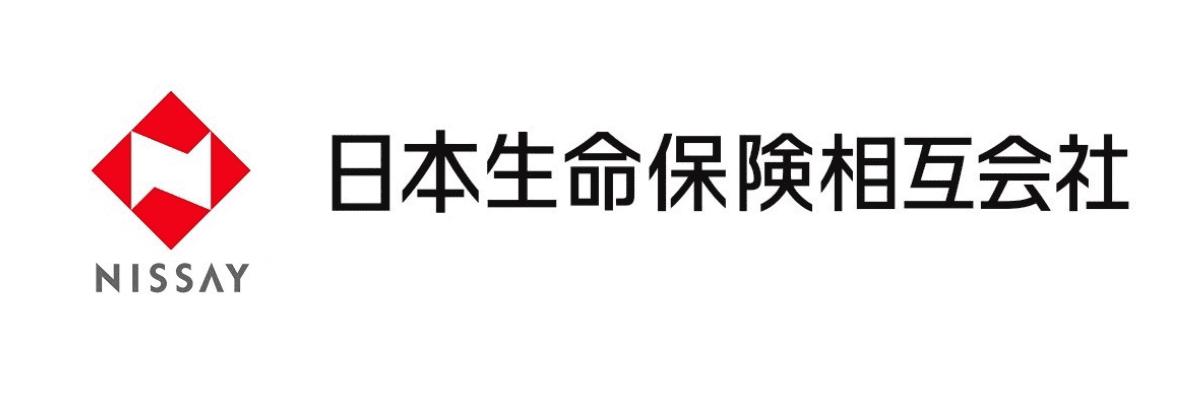【2025年最新】郵便料金は今後どうなる?度重なる値上げの背景や企業が取るべきDX戦略を解説
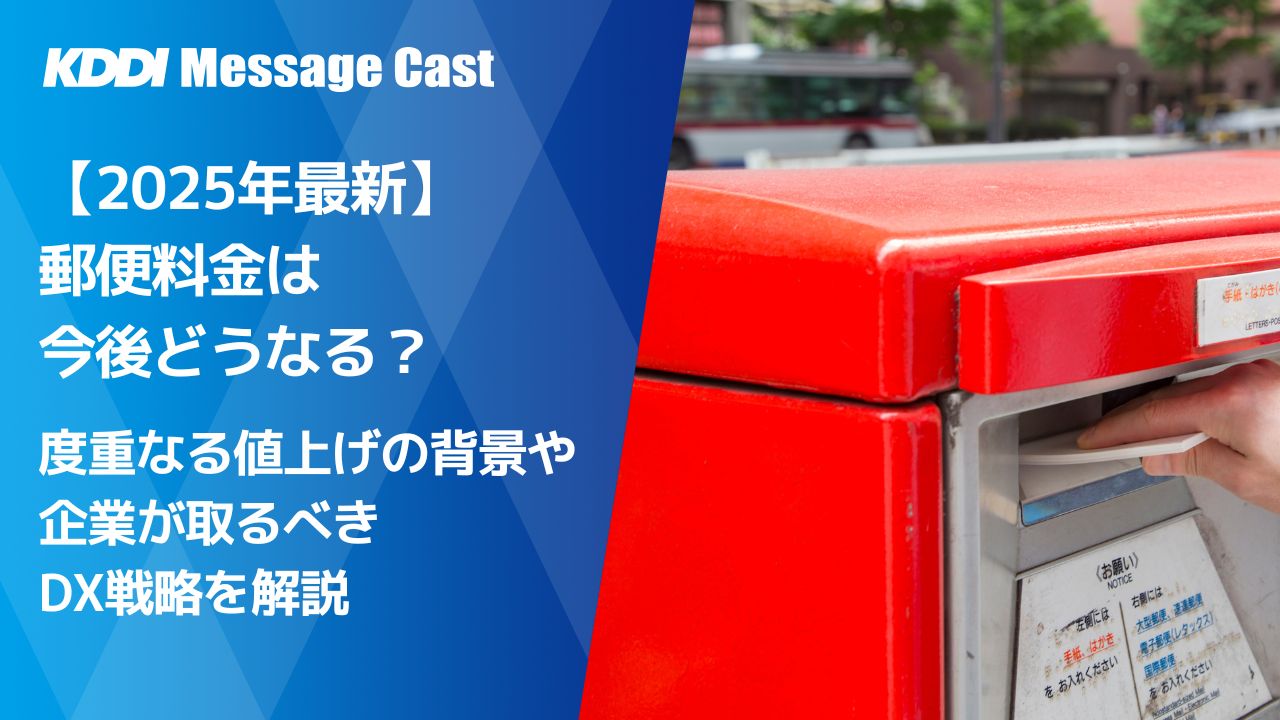
2024年10月、はがきや封書などの郵便料金が大幅に値上げされたことは、多くの企業にとって記憶に新しい出来事でしょう。しかし、この値上げは一過性のものではなく、郵便事業が抱える構造的な課題の表れに過ぎません。2025年現在、総務省の情報通信審議会では、将来にわたる更なる料金制度の見直し議論が進んでいます。
この記事では、2024年の値上げの振り返りに加え、情報通信審議会による最新の資料も踏まえながら、今後の郵便料金の見通しと、企業が今こそ本格的に取り組むべき根本的な対策について、深く掘り下げて解説します。
目次
【振り返り】2024年10月のはがき・郵便料金値上げ
2024年10月1日に、第二種郵便物であるはがきや、第一種郵便物である定形郵便物を中心に、郵便料金が改定されました。
| 郵便物の種類 | 9月30日まで | 10月1日以降 | 値上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 通常はがき | 63円 | 85円 | 22円 |
| 往復はがき | 126円 | 170円 | 44円 |
| 定形郵便物(25gまで) | 84円 | 110円 | 26円 |
| 定形郵便物(50gまで) | 94円 | 110円 | 16円 |
その他、レターパックや速達なども含め、全体的に料金が引き上げられました。この改定は、消費税増税に伴うものを除けば約30年ぶりとなる大幅なものであり、多くの企業でダイレクトメール(DM)や請求書発行などのコストが急増しました。
郵便料金値上げの早見表はこちらから
関連リンク:【2024年10月1日から】郵便料金の値上げを早見表で解説!変更点・対策も紹介
https://kddimessagecast.jp/blog/sonota/240711/
なぜ郵便料金は上がり続けるのか?構造的な3つの背景
2024年の値上げ後も、郵便事業の収支は再び赤字に転じると予測されており、今後も料金改定が避けられない状況です。その背景には、企業努力だけでは解決が難しい、社会構造の変化に根差した3つの要因があります。
1. デジタル化による郵便物数の急激な減少
SNSや電子メールの普及により、コミュニケーションの手段はデジタルが主流となりました。これにより国内の郵便物数は、ピークだった2001年度の262億通から減少し続け、2024年度には125億通と半分以下になりました。
一方で、ライフスタイルの多様化や核家族化などの影響により、配達先の世帯数は増加傾向にあり、一部の配達箇所において「配達すべき郵便物がない日」が発生するなど配達効率は著しく悪化しています。
2. 人件費・燃料費などコストの継続的な高騰
郵便事業は、全営業費用のうち人件費が約75%を占める労働集約型の産業です。近年の賃上げの潮流や、世界情勢を背景とした燃料費の高騰は、事業コストを直接的に圧迫し続けており、この傾向は今後も続くと見られます。
3. 「ユニバーサルサービス」維持の責務
郵便は、法律で「あまねく全国で公平なサービス」を提供することが義務付けられた「ユニバーサルサービス」です。過疎地や離島であっても、都市部と同じ料金で手紙を届けなければなりません。この全国ネットワークを維持するためのコストは、郵便物数が減少する中でも変わらず、事業の重い負担となっています。
これらの構造的な課題から、日本郵便の郵便事業は2022年度に民営化後初の営業赤字に転落し、赤字幅は拡大を続けています。
【今後の見通し】料金はさらに上がる?総務省の最新議論
2024年の値上げだけでは、郵便事業の赤字は解消されず、2026年度以降は再び赤字が拡大する見込みです。この状況を受け、総務省の情報通信審議会では、より柔軟で機動的な料金改定を可能にするための新しい制度設計の議論が進んでいます。
ポイントは、これまでのように国が上限額を細かく定めるのではなく、日本郵便が経営状況に応じて主体的に上限料金の変更を申請できる「上限認可制度」の導入です。これは、一度に大幅な値上げを繰り返すのではなく、社会経済情勢の変化に応じて、より小刻みで段階的な料金改定が行われるようになる可能性を示唆しています。
つまり、郵便料金は今後、物価や人件費の動向に連動して、より頻繁に変動していく時代が到来すると考えられます。
参照:情報通信審議会「郵便事業を取り巻く経営環境等の変化を 踏まえた郵便料金に係る制度の在り方」
https://www.soumu.go.jp/main_content/001022765.pdf
はがきや書類などの郵送対応をアナログで進める際に発生する手間
郵便料金の値上げは直接的なコスト増ですが、見過ごせないのが郵送業務に付随する「見えないコスト」、つまり人的・時間的コストです。デジタル化を検討する上で、これらの間接コストを把握することは非常に重要です。
手順1:送付リストの準備・確認
まず、送付対象者のリストを準備し、氏名や住所に誤りがないかを確認します。リストの抽出やクレンジング作業には専門知識が必要な場合もあり、個人情報を扱うため、慎重な管理が求められます。この初期段階だけでも、多大な時間と注意力を要します。
手順2:文書のデザイン・作成
送付するはがきや同封する書類のデザインを作成します。掲載する情報を選定し、レイアウトを調整する作業は、担当者のスキルに依存しがちです。内容の承認を得るための社内調整にも時間がかかり、軽微な修正でも大きな手間となることがあります。
手順3:印刷・資材準備
作成したデータを基に、はがきや書類を印刷します。大量の場合は印刷業者への発注が必要となり、納期管理やコスト交渉が発生します。また、封筒やクリアファイル、送付状など、郵送に必要な資材の在庫管理や発注も担当者にとって見えない負担となります。
手順4:宛名印字・ラベル貼り
印刷された郵便物一つひとつに宛名を印字、あるいは宛名ラベルを貼り付けます。この作業は単純ですが、送付件数が多ければ多いほど膨大な時間を要します。手作業の場合、宛名の貼り間違いなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
手順5:封入・封かん作業
印刷物や書類を丁寧に折り、封筒へ封入します。送付物が複数ある場合は、入れ間違いがないよう細心の注意が必要です。封入後、のり付けやテープで封かんする作業も、手作業では時間がかかり、非効率な業務の代表例と言えるでしょう。
手順6:料金計算・切手貼付
郵送物すべての重さを量り、規定に従って正確な郵便料金を計算します。その後、料金分の切手を用意し、一つひとつに貼り付けていきます。料金が不足していると返送されたり、逆に過払いになっても返金されなかったりと、正確さが求められる手間のかかる作業です。
手順7:発送(投函・郵便局への持ち込み)
準備が完了した郵便物をポストに投函するか、大量の場合は郵便局の窓口へ直接持ち込みます。持ち込みには移動時間と待ち時間がかかります。また、料金後納郵便を利用する場合でも、発送記録の作成など、付随する事務作業が発生します。
手順8:管理・問い合わせ対応
発送後は、発送記録を保管・管理し、顧客からの「書類が届かない」といった問い合わせに対応する必要があります。不着の場合は原因を調査し、再送手続きを行わなければならず、アフターフォローにも手間とコストがかかり続けます。
【企業のDX戦略】今、本当に取るべき3つの対応
度重なる郵便料金の値上げは、もはや単なるコストの問題ではありません。これは、ビジネスコミュニケーションのあり方を根本から見直す「DX(デジタルトランスフォーメーション)推進」の好機と捉えるべきです。
1. 電子メール・SMSの積極活用
はがきやDMで送付していたお知らせやプロモーションは、電子メールやSMS(ショートメッセージサービス)に切り替えることで、郵送費と作業コストを劇的に削減できます。特にSMSは到達率・開封率が非常に高く、URLを添付すればWebサイトへの誘導も容易です。顧客との接点を失うことなく、より迅速で低コストなコミュニケーションを実現します。
2. 会計・請求プロセスの完全電子化
請求書や領収書の発行・送付を電子化できる会計ソフトや請求書発行システムを導入しましょう。これにより、印刷・封入・郵送といった一連の作業が不要になります。2023年10月から開始されたインボイス制度も電子インボイスに対応しており、法改正への対応と業務効率化を同時に実現できます。
3. カタログやパンフレットのデジタルコンテンツ化
紙媒体で送付していたカタログやパンフレットは、デジタルブックやWebコンテンツとして提供しましょう。メールやSMSでURLを送るだけで、顧客はいつでも最新情報にアクセスできます。改訂時の印刷・発送コストが不要になるだけでなく、どのページがどれだけ見られたかといった閲覧データを収集・分析し、マーケティング施策の改善に活かすことも可能です。
はがきや請求書、カタログを電子化する5つのメリット
| メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| コストの大幅削減 | 郵送費、印刷費、紙代、人件費といった直接的・間接的なコストを削減。 |
| 業務効率の飛躍的向上 | 印刷、封入、発送といった手作業を自動化し、人的リソースをより創造的な業務へシフト。 |
| 効果測定とデータ活用 | 開封率やクリック率、閲覧データなどを収集・分析し、マーケティングや営業活動の精度を向上。 |
| 情報の即時性と更新性 | 価格改定や新商品情報を即座に反映・通知可能。顧客は常に最新の情報にアクセスできる。 |
| 顧客体験(CX)の向上 | スマートフォンやPCからいつでもどこでも情報を確認でき、ペーパーレス化で保管・管理も容易に。 |
これらに加え、電子化はサーバーやクラウド上でデータを一元管理できるため検索性や保管効率が向上し、パスワード設定などでセキュリティも強化できます。紙の使用量削減は、企業の環境保護(SDGs)への貢献にも繋がります。
多機能のSMS送信サービスならKDDI Message Cast for DXハガキ
はがきの値上げを受けて、企業が対策を立てるにはKDDI Message Cast for DXハガキがおすすめです。KDDI Message Cast for DXハガキは、はがきで送付していた情報をデジタルコンテンツに変換するサービスです。はがきの送付内容をWebページとして生成し、SMSでリンク先のURLを送付する仕組みです。
KDDI Message Cast for DXハガキを導入すれば、1通10円から利用できるSMSを活用して低コストで高速な情報の伝達ができます。また、印刷費などのはがきの作成に付帯する費用も抑えられます。さらに双方向コミュニケーションが可能で、既存システムとの連携も可能な多機能ツールであるため、活用してみましょう。
▼KDDI Message Cast(KDDIメッセージキャスト)詳しくはこちら
https://kddimessagecast.jp/
https://kddimessagecast.jp/service/other/dx_hagaki/
まとめ:郵便料金の値上げは、DX推進の合図
2024年の郵便料金値上げは、今後も続く構造的な変化の始まりに過ぎません。総務省の議論が示すように、私たちは郵便料金がより頻繁に変動する時代を迎えています。
この変化を単なるコスト増として受け身で捉えるのではなく、旧来の紙ベースの業務プロセスを根本から見直し、ビジネス全体をデジタル化へと舵を切る絶好の機会と捉えるべきです。SMSや電子請求書、デジタルコンテンツの活用は、コスト削減だけでなく、業務効率化、データに基づいたマーケティング、そして顧客満足度の向上に直結します。
今こそ、郵便料金の値上げを「DX推進の合図」と捉え、持続可能な事業成長に向けた一歩を踏み出しましょう。
「KDDI Message Cast for DXハガキ」の資料をダウンロード(無料)
その他の関連記事
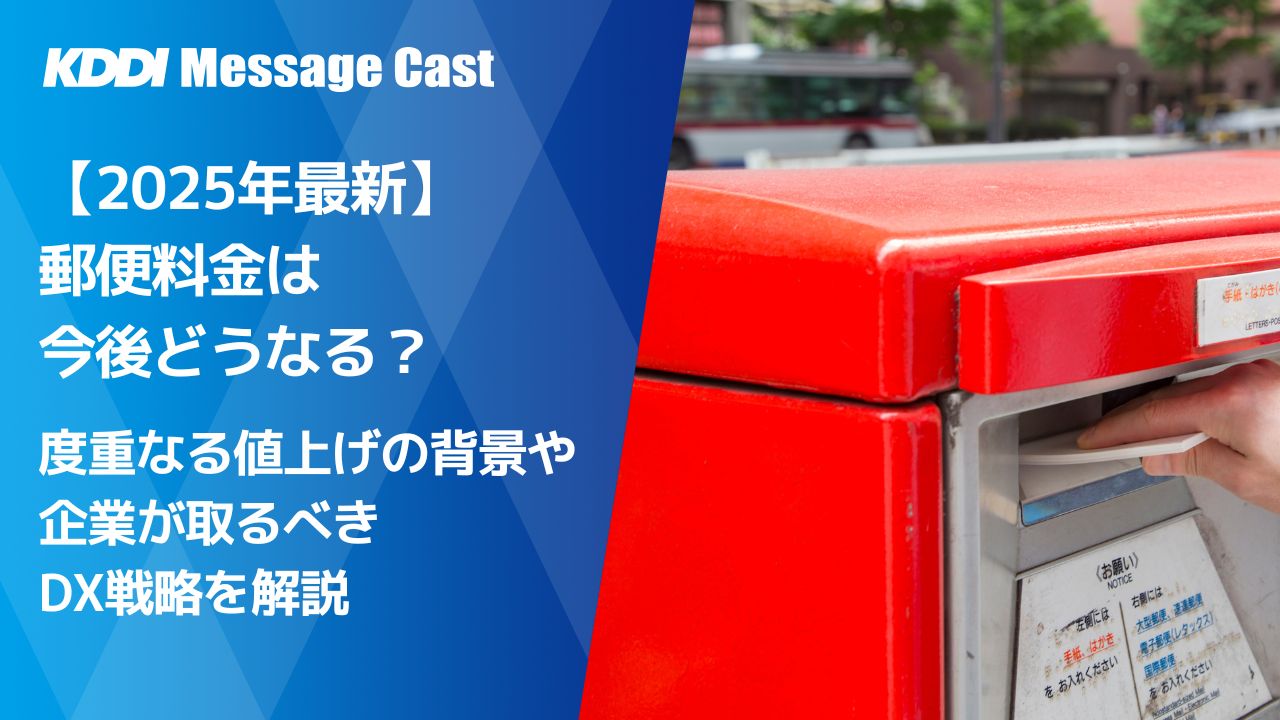
【2025年最新】郵便料金は今後どうなる?度重なる値上げの背景や企業が取るべきDX戦略を解説

電話番号の「090・080・070」の違いとは?携帯番号のパターンや迷惑電話かどうかを調べる方法も紹介

プッシュ通知とは?iPhone・Android別の設定方法や種類、メリット、活用のコツを解説

SMS活用・DX推進セミナー「自動車業界向け SMS活用・DX推進セミナー」
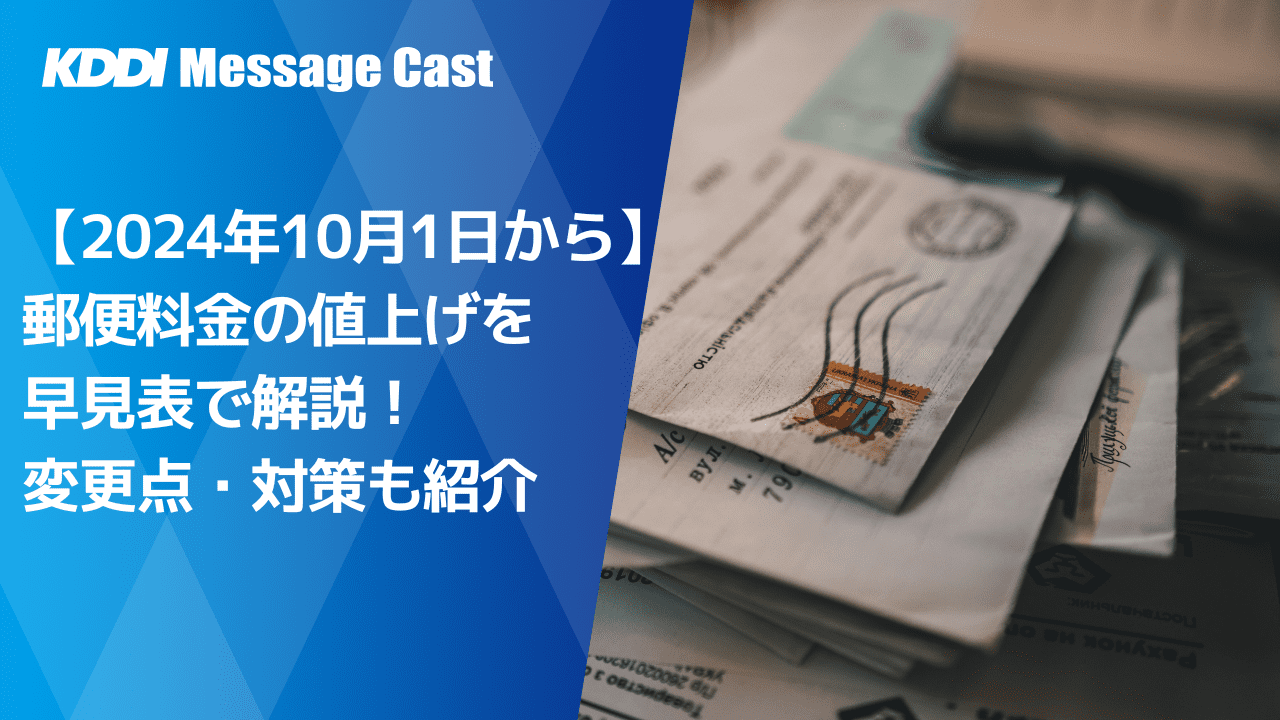
【2024年10月1日から】郵便料金の値上げを早見表で解説!変更点・対策も紹介