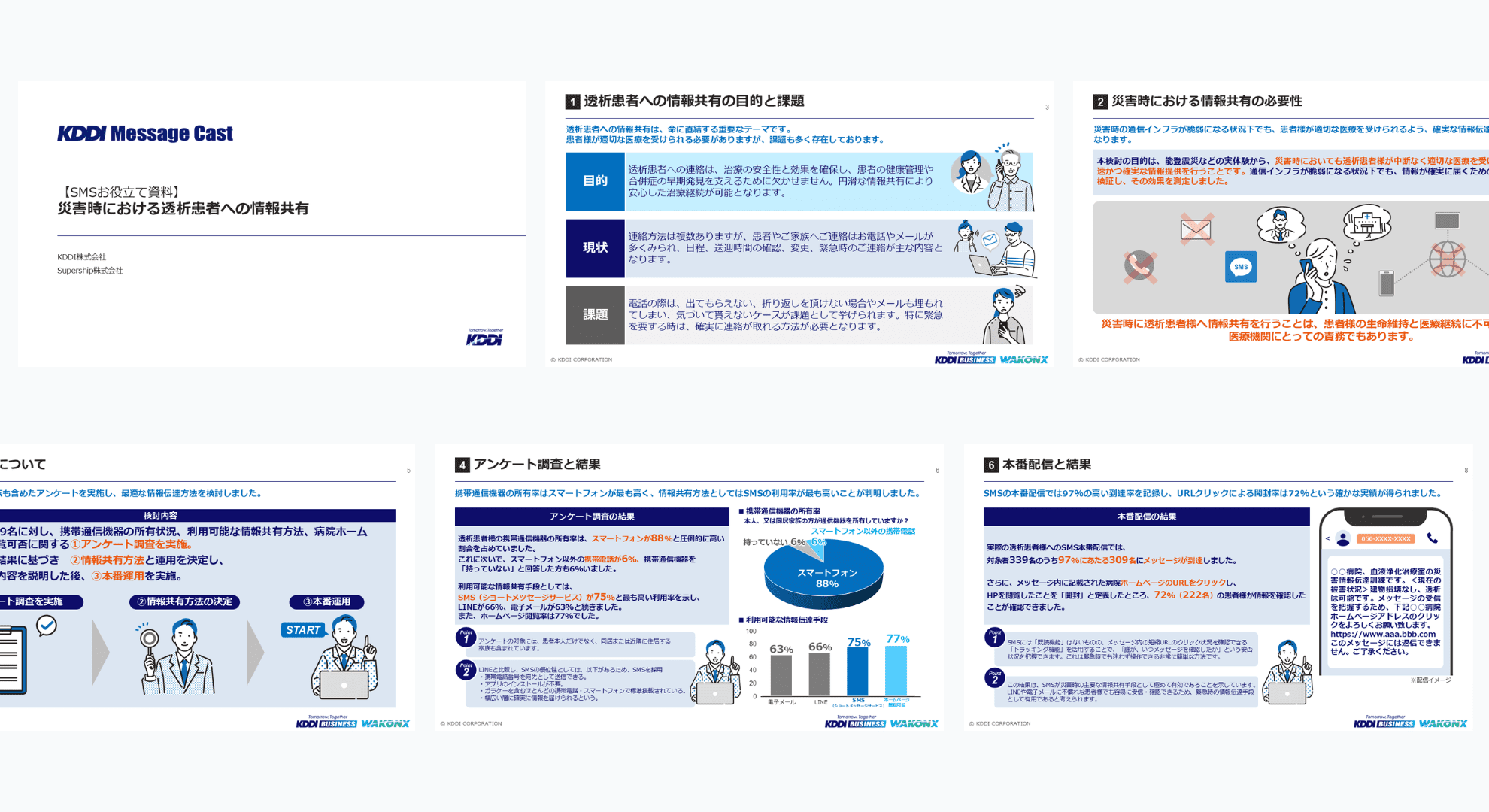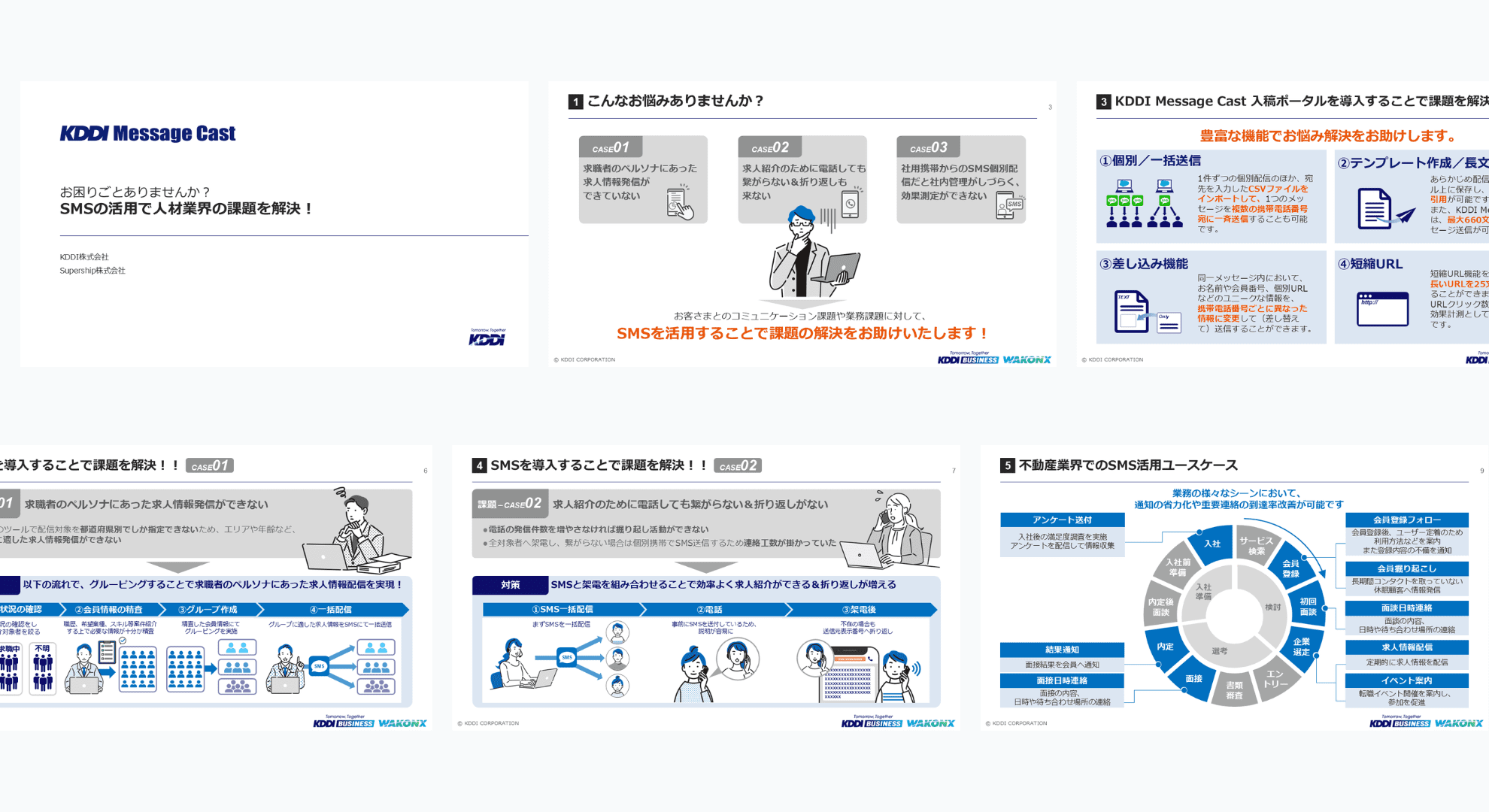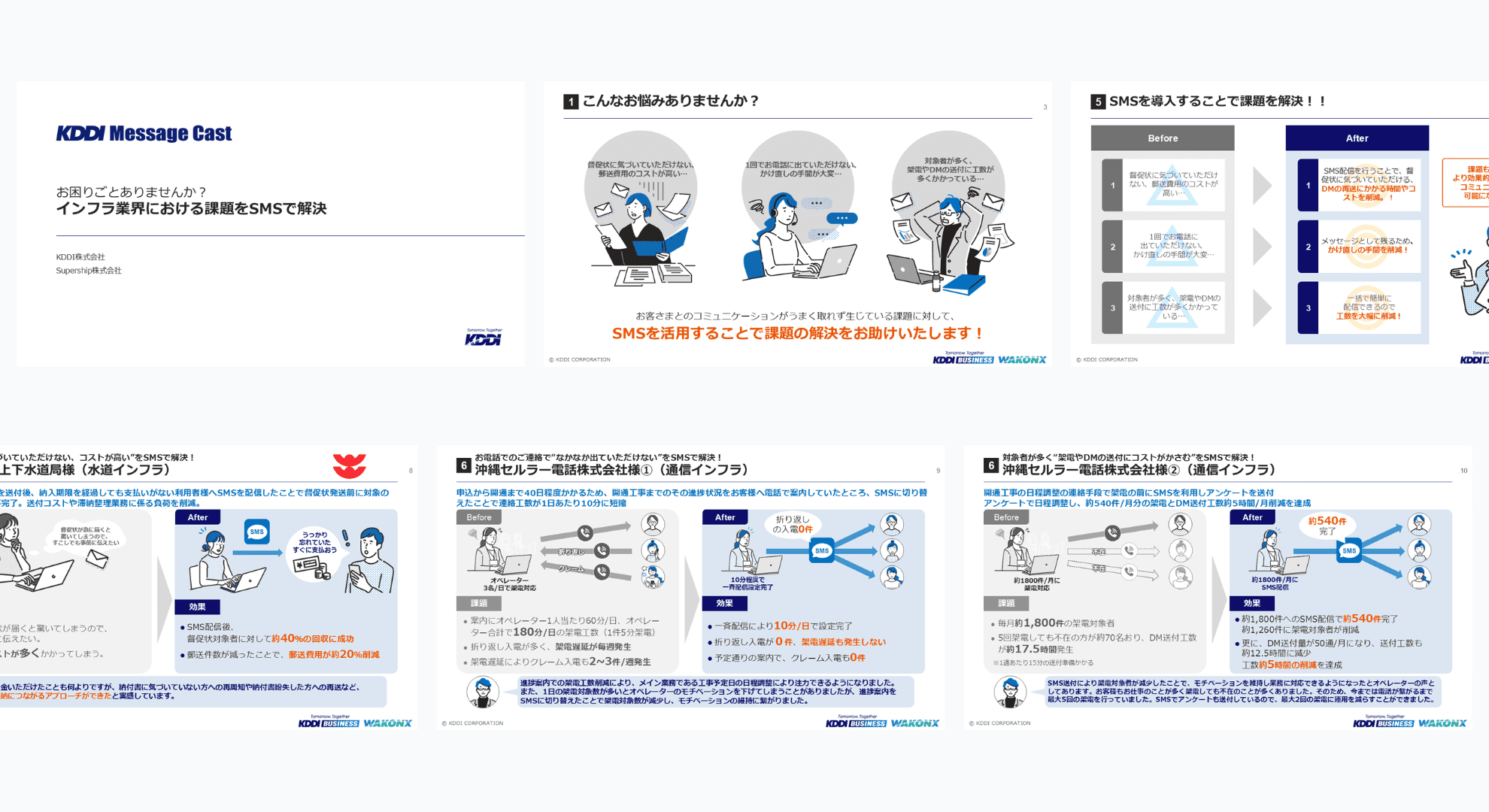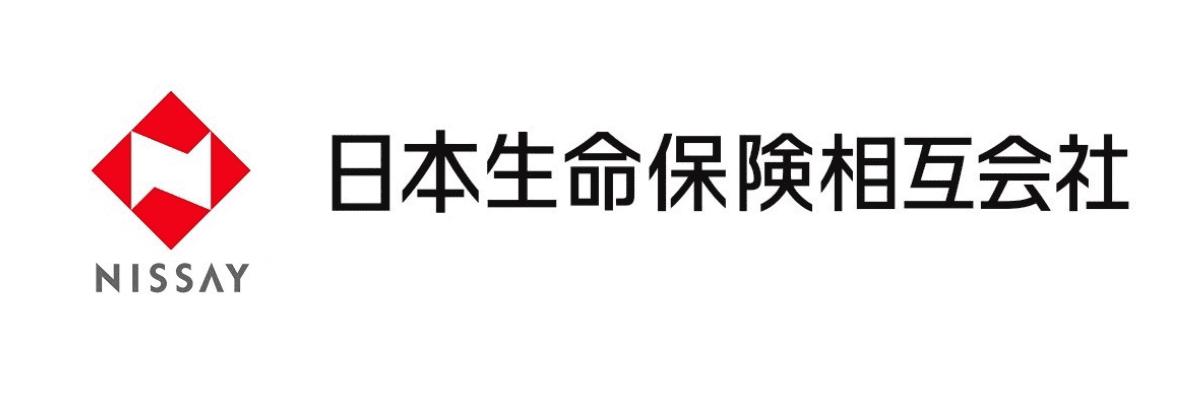大学のDXとは?導入手順や成功のコツ、事例を紹介
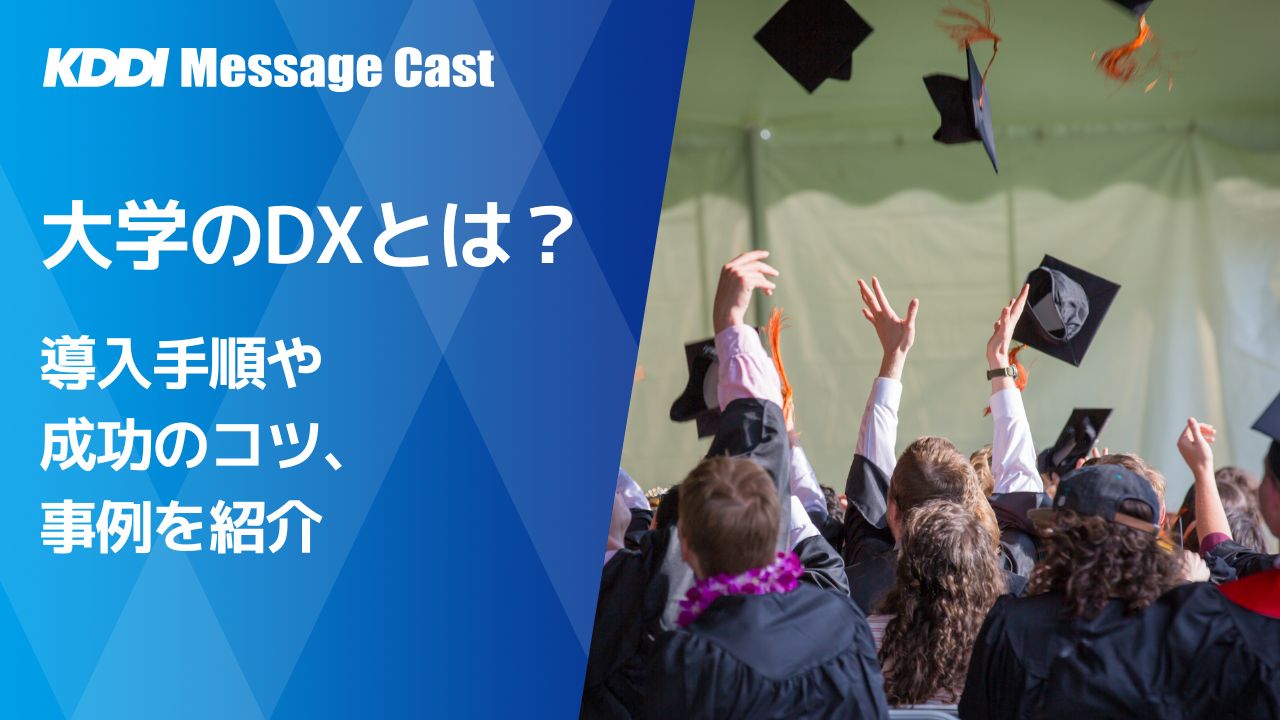
大学ではDX化が求められています。DXの推進に長期的に取り組むことで、学生教育だけでなく経営も効率化できる魅力があります。この記事では大学におけるDX化のメリットと注意点をまとめました。DXの進め方の具体的な手順や、実際にDX化を推進して成功している事例もご説明します。大学でDXを推進する際に有用なSMS送信サービスも紹介しますので、今後の取り組みの際に検討してください。
目次
DXとは?

DXとは近年、急速に発展しているデジタル技術の活用によって変革を起こし、イノベーションによる改革を実現することです。インターネットを皮切りとして発展してきたITはAIやIoTの登場によって更なる進展が起きています。デジタル技術を用いることで新しい価値を生み出せる可能性が広がりました。ビジネスでDXはデジタル技術の活用によって競争上の優位性を確立する方法として積極的な取り組みが進められています。
関連リンク:
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?DX推進のメリットと課題も解説
DXにデザイン思考は必要?重要視される理由や事例を解説
学校でメール配信システムを使うメリットを解説!活用事例もご紹介!
大学でDX化が求められている理由
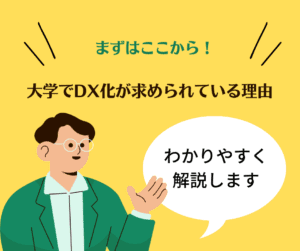
大学でDX化が求められているのは経営効率の向上と学生教育の充実にデジタル技術を活用できるからです。私立大学だけでなく国立大学も大学法人として独自の経営を進められるようになりました。大学の経営効率を上げてコストを削減しつつ、優秀な学生を輩出できる基盤を整えることが求められています。大学経営では限られた収入源で教育・研究の両方を支援しなければならないため、DXによる効率化に注目するケースが増えてきました。
オンライン授業を実施したり、教員と学生がコミュニケーションを取れるようにしたりするだけでも学生の主体的な学習を促進できます。教職員の事務作業を一元的にシステム管理すると全体的な事務効率を向上させることが可能です。このようなIT活用の取り組みだけでも大きな成果につながるため、抜本的な取り組みによるDXでイノベーションを起こし、競争力のある大学に育て上げる取り組みが活発になってきています。
関連リンク:DXはなぜ必要なのか?効果や必要性、進め方を徹底解説
大学のDX化が指すものとは
大学のDX化が指すものとは、優秀な学生を育てるための「学生支援」と、大学内の事務作業をスムーズにする「学校経営の効率化」の二つの要素から成り立っています。
また、この2つをバランスよく推進することが大切です。それぞれについて詳しく説明します。
学生支援
学生支援のためのDXが必要な理由は、以下の4つです。
- 学習環境の向上
オンライン授業やデジタル教材が利用可能になり、学生は時間や場所に縛られずに学ぶことができるようになります。 - 進学先の選択肢の拡大
通学負担が軽減されることで、学生はより多くの進学先を選ぶことができます。 - 経済的負担の軽減
通学費や1人暮らしなどにかかる費用負担が軽減できます。 - 学生獲得の促進
遠方や海外の学生も入学しやすくなり、大学の集客力や大学の魅力が向上します。
また、導入事例は以下の4点です。
- オンライン講義の実施
自宅で受講できる講義が増えているため、学習機会が拡大しています。 - 講義動画の配信
いつでも視聴できる講義動画を提供し、学習をサポートします。 - デジタル教科書の導入
教材をデジタル化することにより、学生がアクセスしやすくなります。 - 各学生の学習の最適化
蓄積された学生のデータを活用し、各学生に最適な学習内容を提供することができます。
今後は、蓄積された履修や成績データをもとに、大学卒業後のキャリアデザインや就職支援、マッチングなどを促進することが期待されます。
学校運営効率化
学生支援のDX化は進んでいますが、学校運営の効率化に向けたDX化はまだ6割以下にとどまっているというデータもあります。それでは、DX化が必要な理由を3点見ていきます。
- 業務生産性の向上
手作業による業務をデジタル化し、教員や職員の手間を削減します。 - 利便性の改善
学生や職員が必要な情報に迅速にアクセスできるようにします。 - 働き方改革の推進
教員や職員の負担が減り、ワークライフバランスが実現できます。
導入事例としては、以下の3点が挙げられます。
- 履修登録・証明書発行システム
ウェブ上で履修登録や証明書発行をオンラインで発行できるシステムの導入。 - 事務作業の一元管理と自動化
学校運営システムを一つのプラットフォームで管理するとともに、請求書や精算システムの自動化を実現。 - 学生対応のデジタル化
チャットツールや専用アプリを活用し、学生からの問い合わせ対応を効率化。
これにより、教員の研究時間や職員の働きやすさも改善されると言えます。
大学でDX化を進める際の手順

大学でのDX化は組織構造に基づいて基本的な手順に従って進めるのが良いでしょう。ここではDXに適している進め方を具体的に紹介します。
目的の明確化と共有
大学でDX化をする際には目的をまず明確にします。デジタル技術を使用して実現したいことをまず大枠として定め、「大学経営にかかっているコストを減らしたい」「学生の減少傾向を止めて選ばれる大学にしたい」「教員による研究を促進する基盤を整えたい」といった目標を掲げましょう。そして、DX化の取り組みについて教職員や学生に情報発信し、目的意識を共有するのが大切です。
課題の洗い出し
DXの目的に応じて課題を洗い出して、具体化を進めます。現状の課題を一通りリストアップしていきましょう。経営者、教職員、学生のそれぞれの視点が必要なので、アンケート調査やインタビュー調査などによる情報収集をした方が良いでしょう。解決すべき課題がまとまったら優先順位を付けます。リソースは限られているので、速やかに解決しなければならない課題を優先してDXに取り組むことが重要だからです。
進めるDX施策の考案
優先して取り組むべき課題が明らかになったら、具体的なDX施策を考案します。目的と課題によって導入すべきデジタル技術も運用方法も異なります。ただ、他の大学でも同じ課題を抱えていることが多いので事例を参考にすると具体化しやすいでしょう。進めるべき施策をリストアップしていき、できるだけ広く課題を解決することが可能な候補を選びます。導入に必要な時間や費用も加味して施策を選ぶとDX化を進めやすくなります。
DX推進体制の構築と組織化
推進するDX施策に応じて適切な体制を構築するのが次のステップです。大学ではDX化の体制整備ができていない場合が多いため、システム管理やデータベース管理などを担当する人材採用から始めなければならない場合もあります。外部委託によって推進体制を構築することも可能なので、状況に応じて円滑に進められる方法を選びましょう。DX施策の進捗管理や評価をするための機能も含めて、組織化して合理的に推進できるようにするのが大切です。
計画の策定・DXの推進
DX推進体制が整ったら計画を立てて取り組みを始めます。予算を立てていつ何をスタートさせるのかを計画し、滞りなくDX化を進めていきましょう。DXによって得られた効果は定期的に確認して評価し、課題点を洗い出して新たに施策に取り入れていきます。計画変更があり得ることも加味して、柔軟に対応できるようにDX計画を策定するのが重要です。少なくとも3年~5年程度の計画を立てた上で、四半期〜半年に一度は見直しをしましょう。
関連リンク:DX戦略とは?立て方や推進プロセス、成功のポイントもご紹介
大学でのDX化を成功させるためのポイント
大学でのDX化を成功させるためのポイントは、以下の3点です。
- まずは小さなステップから始める
- 目的を明確化・ツールに依存しない
- 作り出せた時間を有効活用する
それでは、詳しく見ていきましょう。
まずは小さなステップから始める
大学全体でDX化を一度に進めようとすると、非常に大きなプロジェクトとなり、完了までに何年もかかるうえ、システムに不具合が発生すると大学全体や学生方に影響が及びかねません。
そのため、まずはゼミや学科内などで小さくテスト運用することをおすすめします。予算を抑えた小規模なスタートから、小さな成果や同じチームの人達の承諾が得られた段階で、次のステップとして学科→学部→大学全体へと順次導入を拡大しましょう。
目的を明確化し、ツールに依存しない
DXが失敗する原因の多くは、デジタルツールを導入すること自体が目的になってしてしまう点です。そのため、まずは「何をどう改善したいか」をDX導入検討メンバー間で認識・共有しておくことが大切です。
例えば、業務時間の短縮やコスト削減、受付業務の効率化など、具体的な目的を明確に設定します。導入後も定期的に実現状況をチェックし、必要に応じて見直すことで着実にDXを定着させることができます。
作り出せた時間を有効活用する
例えば、学生対応のシステムを導入することで、従来職員が窓口で学生の対応に費やしていた時間を大幅に削減することができます。そのDX化により創出された時間を活用し、教育プログラムや学校運営改善に取り組むと良いでしょう。
このように、システム導入前に使っていた時間の活用を意識することがDX化の効果を最大限に引き出し、さらには、学習環境の改善や学生満足度の向上に繋がります。
大学がDX化を進めるメリット

大学がDX化に取り組むと費用対効果の高い成果が得られます。具体的なメリットをまとめたので確認していきましょう。
教育の質を向上させられる
DX推進によって大学では教育の質を上げられます。オンライン授業や学習状況の把握などが可能になると学生の主体的な学習を促進可能です。AIによる授業選択の提案や関連する講義・ワークショップのオンライン開催などを通してさまざまな形で学生をサポートできます。また、教員にオンライン教材を使って教育をする機会も提供できるのも重要なポイントです。データを用いて学習効果の上がる方法を検討できるシステムも整えれば、教育の質を上げる取り組みを進めやすくなります。
学生・教職員が自身の状況を可視化できる
DX化によって学生や教職員の評価をデータベース化して視覚的にわかりやすく本人が確認できるシステムを整えられます。学生にとっては自分の成績が大学内でどの程度の位置付けになっているかを分析したり、適性を判断したり、卒業研究のゼミや研究室を選んだりする上で重要な情報源です。教職員にとっては教育・研究のそれぞれについて取り組みの状況や大学からの評価を把握できるため、今後の改善点を探るのに活用できます。
さまざまな地域の学生を集められる
学生にとってDX化が進められた大学には魅力があります。授業のオンライン化が進み、卒業研究などもリモートで実施できるならキャンパスが遠くても問題ありません。遠くの大学でも進学できるため、広い候補から自分に合う大学を選べるようになります。下宿費用などの悩みがあって実家から通える範囲の大学しか選べない人もたくさんいます。大学ではDX化に取り組むとさまざまな地域の学生を集められるようになるのがメリットです。
コストを抑えられる
大学ではDX推進を通してコストを抑えられるようになります。大学の運営システムを一元化して自動処理を導入すれば事務手続きが効率化されます。学生対応にチャットやアプリを利用すれば窓口対応の負担を減らすことが可能です。履修登録や在学証明書の発行手続きなどもシステム上で行えるようにすると事務負担が減るだけでなく、学生にとっても快適な環境が整えられます。講義の実施による光熱費もオンライン化によって圧縮できるなど、さまざまなコスト削減につながるのがDXの魅力です。
研究活動の質を向上できる
研究DXを実現し、研究活動の質を向上させるのは大学にとって重要なポイントです。DXによってデータに基づく研究を促進するインフラを構築することで、研究に必要なデータを容易に取得できるようになります。文献調査や公開情報調査などにかかる時間と労力は大きく、ビッグデータからの検索が容易になることで、研究活動を効率化させることが可能です。
また、オープンサイエンスや産官学連携なども研究活動において重要になっています。各研究機関の活動内容がデータ化されて共有されることにより、共同研究の機会を増やし質を高められるようになります。
職員のキャリア形成ができる
大学のDXは大学経営を支えている職員のキャリア形成につながります。大学の経営、財務、経理、人事、総務などを担っている職員たちは転換期を迎えています。今までの公務員的な働き方から考え方を変えて、効率を重視して価値を生み出す大学経営を実現しなければなりません。
大学がDXに取り組むことによって、現場でDX推進に携わってきたことが職員のキャリアになります。キャリア形成を見据えた働き方は現代のトレンドです。DXを積極的に推進することによって、大学職員にとって魅力的な職場を提供することができます。
若者への教育機会の提供
教育DXによってこれからの社会を担う若者に多様な教育機会を与えることができるのもメリットです。例えば、所属している大学の教員による授業だけでなく、他の大学の教員や企業、公的機関などの有識者の講演をウェビナーで気軽に受講する機会を与えられます。また、リモートで授業を受けられるようになることで、遠方に住んでいる若者にも下宿費用の負担をさせずに希望する大学で授業を受けて学べる環境を提供することが可能です。
また、大学で簡単にITを利用できるインフラを整えることで、卒業研究や大学院研究で活用できるようになります。海外の研究者にインタビューをするなど、さまざまな取り組みをして経験を積むことが可能です。自発的に物事に取り組む若者を育て上げる機関として大学が機能するためにDXが必要な時代になっています。
関連リンク:DXを推進するメリット・デメリットとは?必要な理由や課題、取り組み方を解説
大学でDX化を進める際のデメリットや注意点

大学ではDX化の目的や課題を考える時点で注意した方が良いポイントがあります。以下の3点に留意して具体策を考えましょう。
教育・研究・経営の連携が欠かせない
大学では教育・研究という2つの機能があります。DX化では経営も加味して教育・研究・経営の連携をしなければ成功するのが難しいため、注意しましょう。DXによる経営の高度化を進めたとしても、教育現場が付いてこられなかったら教育の質は上がりません。教育中心でDXを進めた結果、教員が研究に割く時間がなくなって成果が上がらなくなるリスクもあります。全体のバランスを考え、調和性のあるDX戦略を導き出すのが大切です。
初期コストが大きい
大学でDX化を推進する際にはDX人材の獲得やシステム開発などの初期コストが大きいため注意が必要です。人材獲得に時間がかかってDXを進められない場合もあります。デジタル技術に強いDX人材はビジネスでも必要とされているため、獲得競争が激しいのが現状です。優秀な人材が見つかっても希望給与が高くて予算的に雇えず、施策が先送りになる可能性もあります。国による補助金・資金支援を得るなど、DX化のための資金調達は早期に始めておくのが無難です。
長期的な取り組みが必要になる
DXは長期的に取り組まなければ効果がはっきりと見えてきません。オンライン授業のためのシステムの導入は数ヶ月でできますが、教員がオンラインで質の高い授業をできるようになるには時間がかかります。新しいシステムを導入するとトラブルも発生するので、対処を繰り返さなければなりません。少なくとも3~5年はDX化の取り組みを続けて評価を実施し、改善も並行して進めていくことが必要になります。
大学のDX推進は高等教育の高度化につながる
大学がDXを推進すると新しい価値を創出して他にはない大学教育を提供できるようになり、高等教育を高度化することができます。大学が法人化された影響を受けて、経営のあり方について自由度が高くなりました。独自の取り組みによってDXを推進することで、学生から選ばれる教育・研究の基盤を作り上げ、職員として働きたいと思う人を集められる大学にすることができる時代になっています。
文部科学省でも「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」を策定して公募を実施して対象機関を選定しています。例えば、東京大学では「東京大学キャンパス・マネジメント・システム(UTokyo CMS)の構築」、横浜市立大学では「テーラーメード型学修支援プラットフォームの構築」といった取り組みを明確化して、公的支援を受けながら大学のDXを推進しています。
大学における高等教育の高度化は学びの質を向上させ、学生本位の教育を推進することにつながります。今後の社会を担う若者に高度な教育を提供し、優秀で自発的に物事に取り組む人材を輩出することは大学の役割のひとつです。DXには資金が必要なのは確かですが、国による支援も受けられるため積極的に大学DXに取り組みましょう。
参照:デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン:文部科学省
大学のDX推進はDX人材の育成が不可欠
大学ではDX推進を担う人材の確保が大きな課題です。DX人材としてデータを効果的に活用できる人がいなければDXは進められません。大学の教育、研究、経営という3つの柱をすべて理解し、DXを推進できる人材は希少でしょう。多くの企業でDX人材の獲得に苦労している状況もあるため、対応力の高い人材を採用して確保することは容易ではありません。
教育DXや研究DXのあり方も変わっていく可能性があります。大学では大学の事情に合わせたDX人材の教育を実施していき、内部で必要な人材を育て上げていくことが大切です。
DX化を推進している大学事例
大学でのDX化の事例は施策を具体化する上で参考になります。ここでは今までに推進されてきた大学事例をご紹介します。
東京大学
東京大学ではオンライン授業・Web会議のポータルサイトとして「utelecon」を運営し、授業・学務・メールサービスなどの一元化をしています。uteleconの活用では授業のグッドプラクティスの共有やオンラインでの授業情報交換会の開催が代表例です。また、東京大学では2022年度からBYOD(Bring Your Own Device)方針を定め、学生に自分のパソコンを持つことを必須条件にしました。オンラインでのコミュニケーションを促進し、DX人材を育てる基盤を整えています。
東京大学は「Beyond AI」をソフトバンク株式会社と共同設立し、AIを基盤とする学術分野の創出や基礎研究を進めるなど、多角的にDX化を推進しています。
近畿大学
近畿大学では「KICSオンデマンド授業」を取り入れています。KICS(Kindai Creative Studio)は音響設備の整ったスタジオで、オンデマンド授業の撮影をするために設置されました。KICSオンデマンド授業によって品質の高い授業をいつでも受講できるようになりました。学生アンケートでも評価が高く、拡大が希望されているサービスです。
また、AIチャットボット「PEP」を全学で導入し、学生・教師職員からSlackでの質問に自動応答するシステムも整えています。近畿大学ではTwitterやInstagram、FacebookやLINEの公式アカウントの運用にも取り組み、幅広いDX化を進めています。
京都大学
京都大学ではDX人材の教育とDXの活用に力を注いでいます。DX人材の教育では産官学連携プログラムとして「情報学ビジネス実践講座」を設けてITリテラシーやビジネス経営、イノベーションのコースに加えて、集中講義やセミナーを受講できるようにしています。京都大学の自由で学生が主体として活動する校風を活かし、学生がDXを推進できる基盤を整えているのが特徴です。
DXの活用では国際MOOCプラットフォーム「edX」のコンテンツとして「KyotoUx」を設置し、講義の一部をオンライン受講できるようにしています。留学生向けのオンライン授業で、大学のグローバル化にも貢献する取り組みになっています。
大阪大学
大阪大学では公式アプリ「MyHandai(マイハンダイ)」の活用によるDXを進めています。もともと大阪大学ではポータルサイトの運営によって教員の事務を取り扱うSSOシステムを運用していましたが、MyHandaiの導入によって教職員と学生のシームレスなつながりを作り上げることに成功しています。
MyHandaiでは学務情報システム「KOAN」で授業の開講状況やシラバスの確認をしたり、学内連絡バスの情報を調べたりすることが可能です。学外の人もMyHandaiに登録可能で、学生マガジン「まちかねっ!」の配信や「アプリdeオープンキャンパス」などのイベント開催を通して広報活動にもアプリを活用しています。
関連リンク:【DX導入事例14選】DX成功事例に見るDX推進のポイントは?
東海国立大学機構
東海国立大学機構は東海地方の名古屋大学と岐阜大学が統合して生まれた「知とイノベーションのコモンズ」としての発展を目指している機構です。デジタルユニバーシティ構想の構築やDEIB宣言なども行いながら、先進的な取り組みを続けています。
東海国立大学機構ではリモート会議の導入やオンライン講義の実施、ウェビナーの開催などのデジタルによる大学変革を進めてきました。デジタルユニバーシティ構想ではデータ基盤と次世代認証基盤を取り入れるDXを想定して取り組みを進めています。東海国立大学機構では地域との協力や産官学連携にも力を注いでいて、「地域まるごとDXする」という考え方でDX推進をしています。
東京学芸大学
東京学芸大学では教育インキュベーションセンターがDXを積極的に推進しています。大学だけでなく教育委員会、企業、東京学芸大学附属校の教員らによって構成されている「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」によって、さまざまな最新技術を取り入れたDXが試みられています。
東京学芸大学ではGIGAスクール時代の学習のあり方を考え、将来的にあるべき教育の姿を実現するために多角的なIT活用をしているのが特徴です。例えば、VR/ARを学習に活用するプロジェクトを起ち上げ、VRヘッドマウントディスプレイ(VRHMD)によって天動説と地動説を体験して理解する教材開発を検討しています。オンライン授業も積極的に取り入れて、教育の機会を広げる取り組みを続けています。
香川大学
香川大学では学業や研究だけでなく、学内で必要になる業務全般の効率化を実現するためのシステムを内製化してDXを進めています。香川大学ではDXラボを組織して、「仮説検証型アジャイル開発」を推進する体制を整えました。大学の構成員として重要な教員、学生、職員の協働によるシステム開発を行い、本当に必要なシステムを整えるインフラを作り上げています。
例えば、香川大学では通勤届申請システムや教員向け休暇申請システム、欠席届申請システムなどを開発して運用しています。業務UX調査によってユーザーニーズを調査したり、業務改善のアイデアを引き出すための業務改善アイデアソンを開催したりするなど、全学でDX推進をするリード機関としてDXラボが活躍しています。
法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
大学のDX化ではSMS送信サービスの導入もおすすめです。SMSによって学生や教職員にダイレクトに情報を伝えられるシステムを整えられます。履修登録や授業料の振込を忘れている学生にリマインドをしたり、新しいDX施策の開始を全構成員に一斉通知したりする手段としてSMS送信は有効です。KDDI Message Castは低コストですぐに導入できる法人向けSMS送信サービスです。一斉送信や既読確認などの機能も豊富なのでDX施策の一つとして検討してください。
Salesforce連携
DX関連 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
まとめ
大学のDX化は教育の質を向上させながら経営を効率化できるメリットがあります。全国的にDX化が進められていて、成果につながった事例も増えてきました。学生に選ばれるランキング上位の大学になるのは少子化が進む現代日本では重要な課題です。DX推進は大学経営を安定化させ、学生・教職員の満足度を向上させる取り組みになります。デジタル技術による課題解決の可能性が広がっているので、DXを進められる体制を整えて積極的に推進していきましょう。
DX関連の関連記事

物流DXの課題解決にSMS活用が必須!物流業界のDX推進事例と成功ポイント
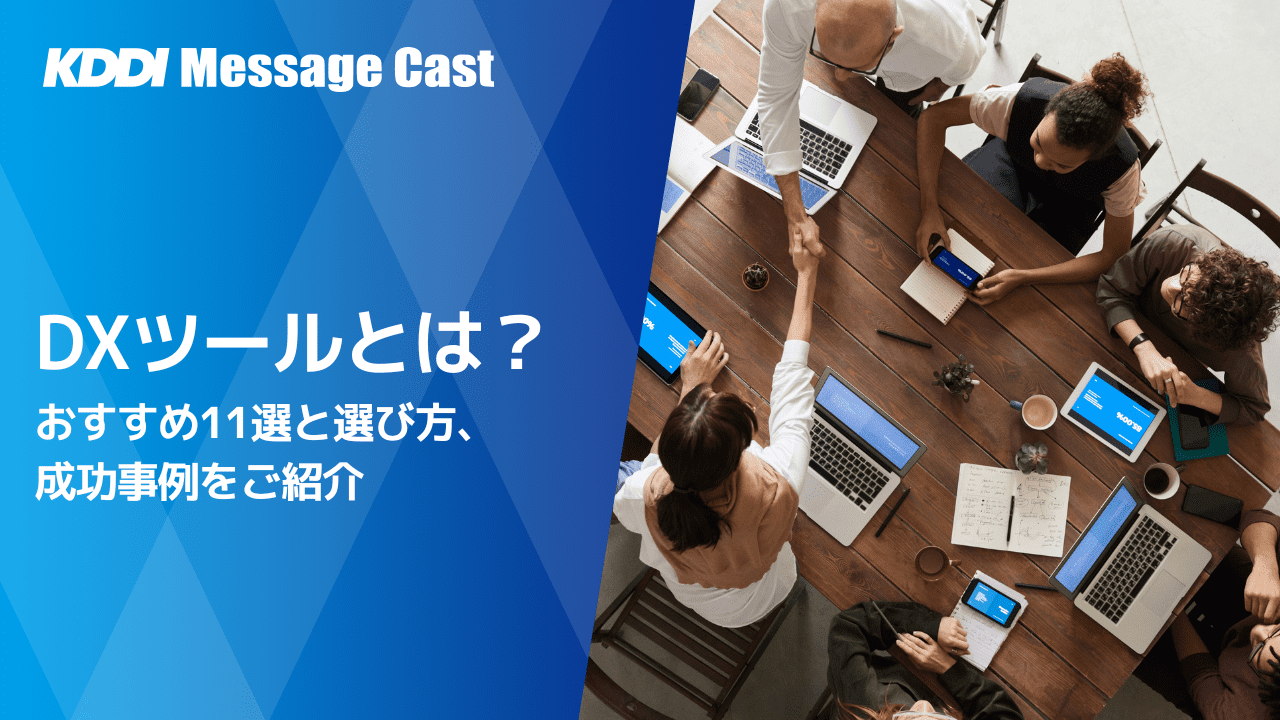
【2025年版】DXツールとは?おすすめ11選と選び方、成功事例をご紹介

エネルギー業界のDX「5つのD」とは?インフラ分野のSMS活用事例とコスト削減効果
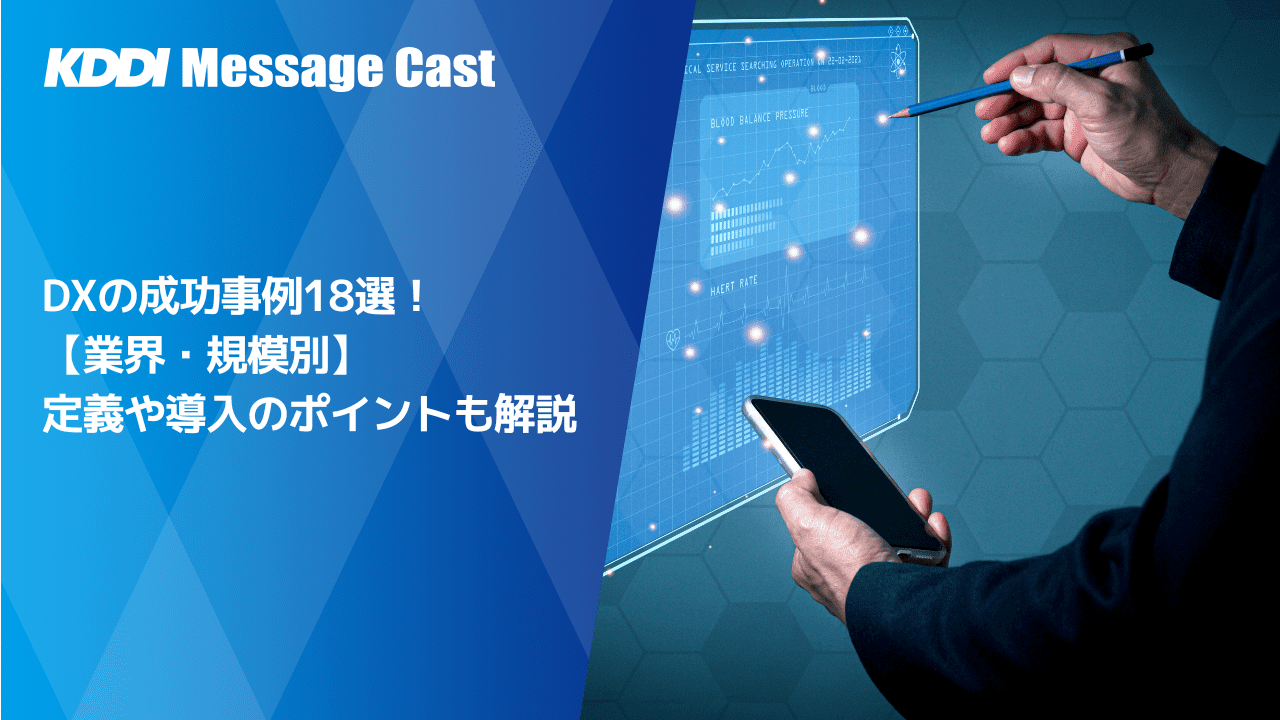
DXの成功事例18選!【業界・規模別】定義や導入のポイントも解説

建設DXとは?導入メリットや課題は?DX化の進め方や事例を紹介