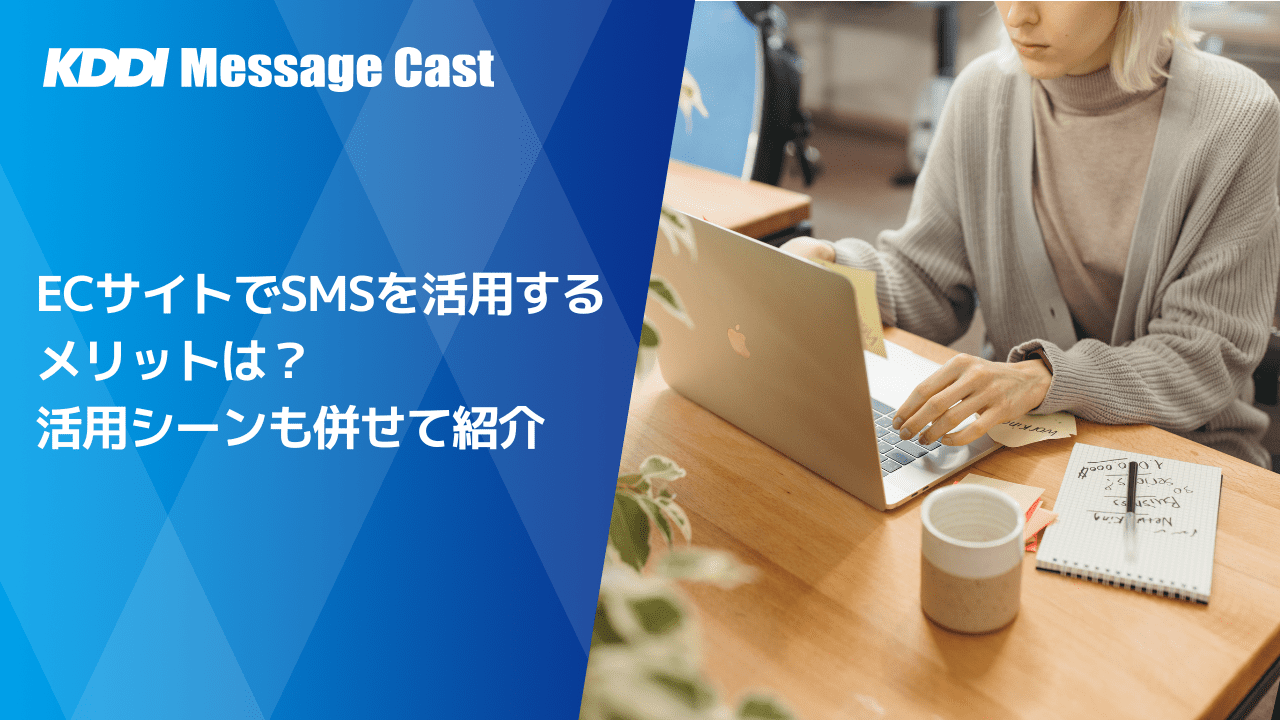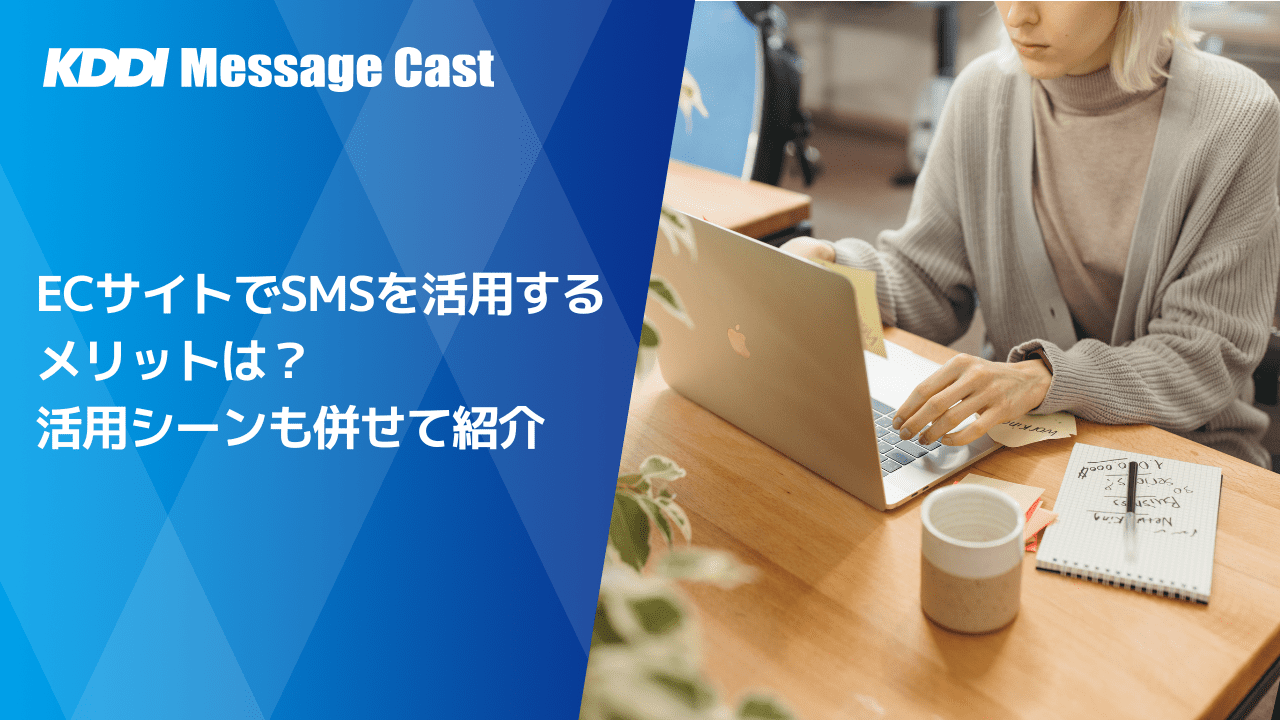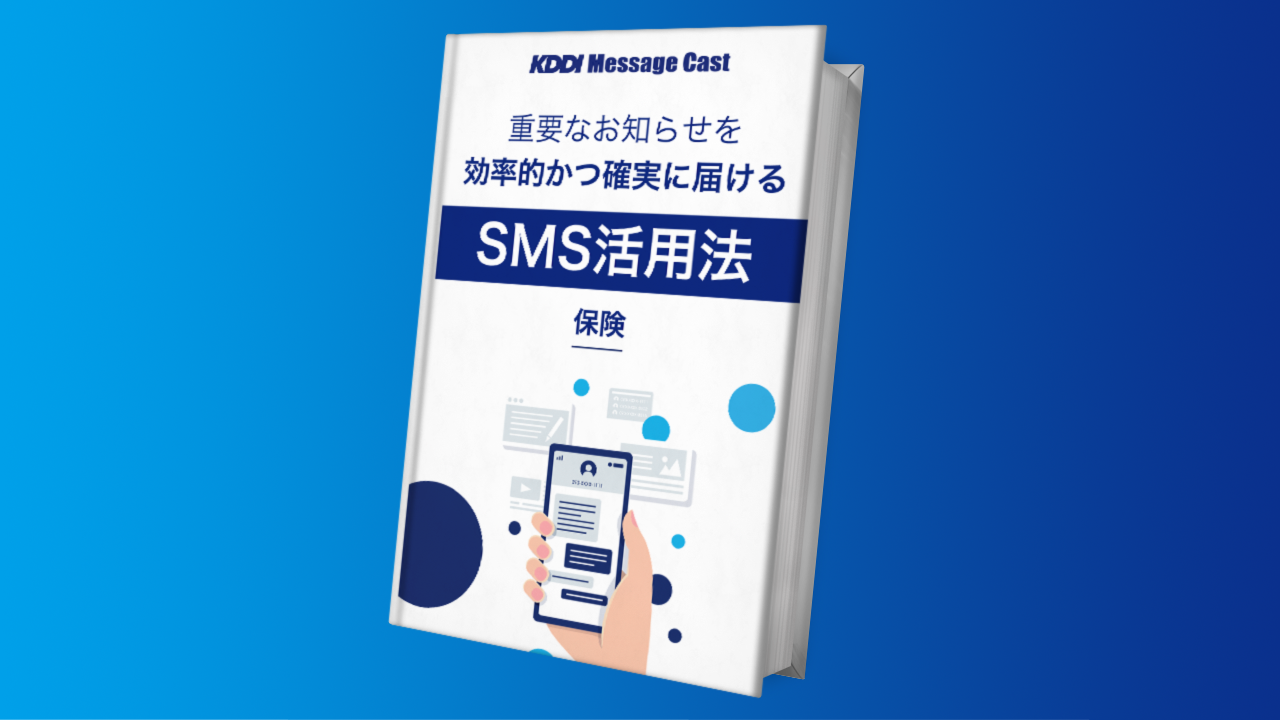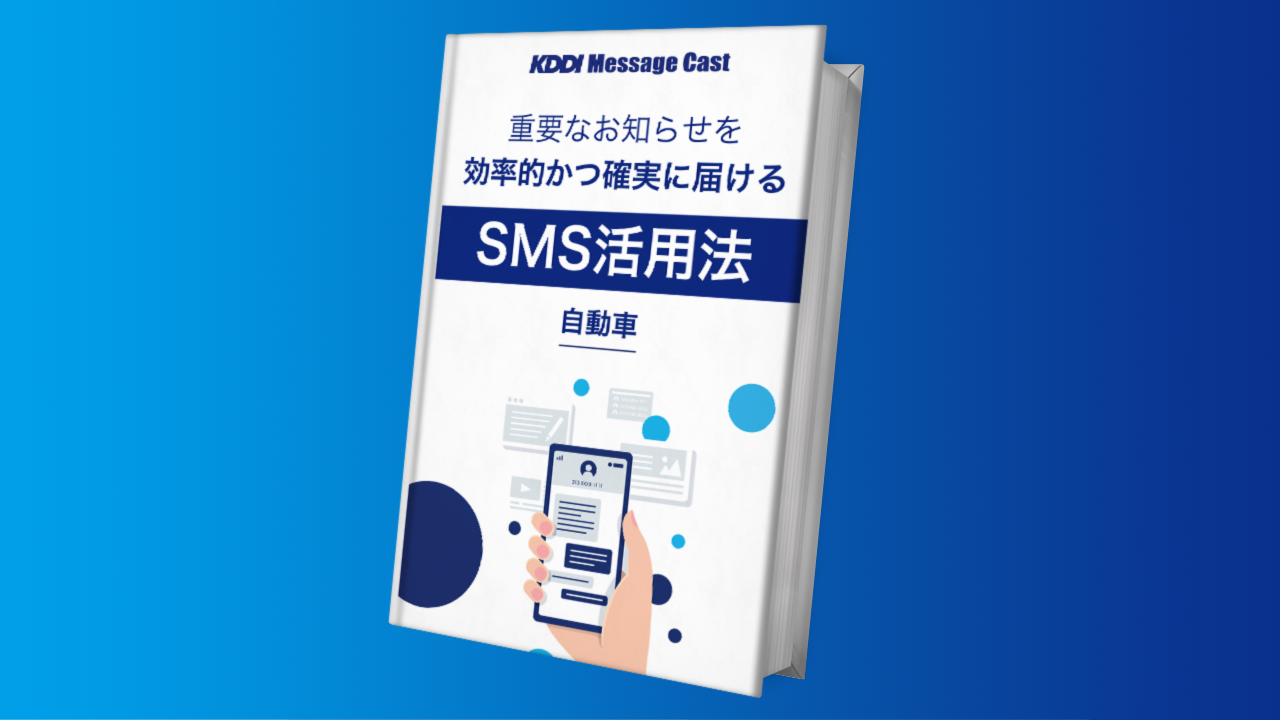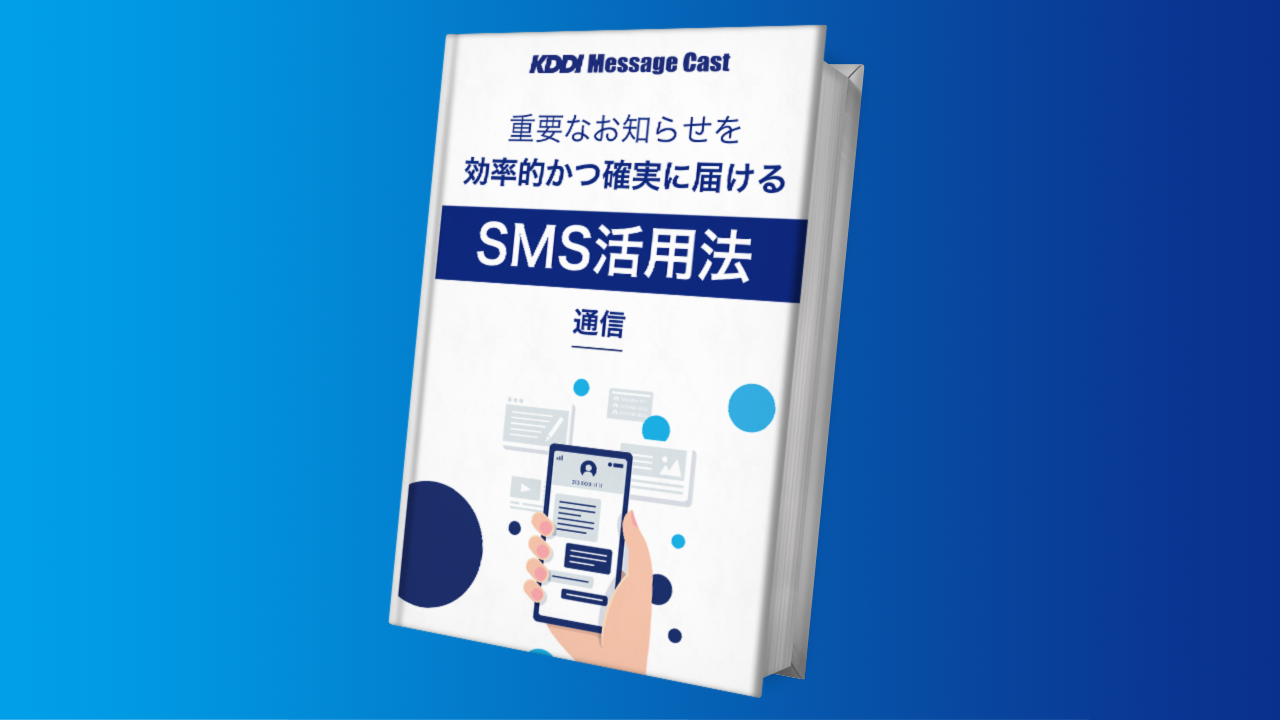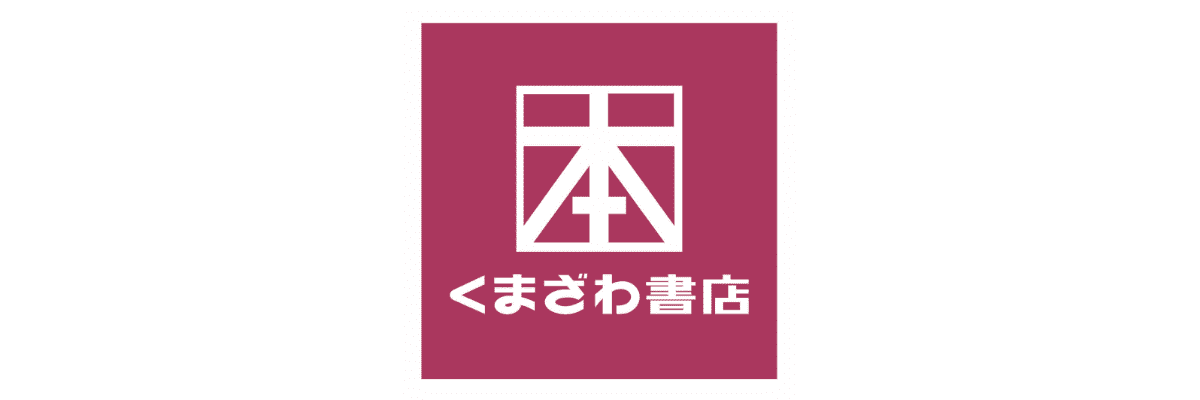SMSの活用事例12選!マーケティングのポイントやメリット、デメリットを徹底解説

ビジネスシーンにおけるSMSの活用が進められるようになり、SMSマーケティングも広く展開されています。SMSを活用してビジネスチャンスを手にしたいなら、SMSマーケティングは効果的なアプローチの1つです。この記事ではビジネスシーンにおけるSMS活用のメリットやデメリット、具体的な事例についてご紹介します。有用性の高いマーケティングのアプローチとしてぜひご検討ください。
目次
SMSマーケティングとは?


SMSマーケティングとは、ショートメッセージサービス(SMS)をコミュニケーションツールとして用いるマーケティング施策です。SMSはスマートフォンやフィーチャーフォンで送受信できる短い文字数のテキストメッセージで、多くのキャリアの端末で共通システムとして利用できます。携帯電話番号をメッセージの宛先にするのがSMSの特色で、個人と一対一の対応になっていることからDMのように活用できる連絡手段として注目されています。
SMSは顧客の電話番号に対して送信するため、顧客は自分のための情報だと期待してくれます。魅力的な情報をSMSで送ってもらえたら、すぐに行動を起こして商品やサービスの購入をしてもらえるかもしれません。Eメールや電話のように即時で顧客にアプローチできることから、効果の高いマーケティング手法としてSMSの活用が進められています。
そもそもSMSとは?


SMSをマーケティングに活用するには、SMSそのものの特徴も理解しておくことが大切です。ビジネス視点で見ると、SMSには次のような特徴があります。
- 携帯電話番号だけで送信できる
- 開封率が高い
- 幅広く普及している
- 文字数や画像の使用に制限がある
- 一斉送信ができる
SMSは携帯電話番号だけで送信可能で、番号の変更が少ないため長期的な連絡手段として有効です。また、通知機能や信頼性の高さから開封率が約80%と高い点もメリットです。さらに、キャリアや機種を問わず利用でき、一斉送信機能を使用すれば幅広いユーザーにまとめてアプローチ可能です。
2019年以降、1つのメッセージで全角670文字まで送信できるようになりましたが、一部の古い機種では全角で70文字を超えると分割で届くため、長文を送る際は注意が必要です。また、画像や動画が送れないため、メールなどに比べると情報量は少なめです。
関連リンク:https://kddimessagecast.jp/blog/sms/sms_merit/
SMSがビジネスシーンで必要とされる背景
ビジネスシーンでSMSが重要視される背景には、その「確実な到達率」と「高い開封率」があります。携帯電話番号は変更されにくく、メールのように大量のメッセージに埋もれることなく顧客に情報が届くため、その視認性は圧倒的です。
さらに、特別なアプリが不要で幅広い層に手軽に利用できる点や、コスト効率の良さ、本人認証に活用されるセキュリティの高さも、企業がSMSを積極的に導入する大きな理由となっています。
SMSを導入するメリット
SMSの特徴がわかると、ビジネスシーンにおける活用範囲が広いと感じた方も多いのではないでしょうか。ここではSMSを導入するメリットを詳しくご紹介します。
関連リンク:https://kddimessagecast.jp/blog/sms/sms_merit/
すぐに見てもらえる
SMSはプッシュ通知を設定していることが多いので、送信してからすぐに見てもらえるのがマーケティングに活用するメリットです。統計的に、開封までの時間が3分程度とされているため、タイムリーな情報を伝えたいときにうってつけです。
レスポンスが良い
SMSはユーザーからのレスポンスが良いのがメリットです。マーケティングでは情報を発信してもレスポンスがなければ意味がありません。レスポンス率は45%といった統計データもあり、SMSマーケティングは効果が上がりやすい方法です。
コストパフォーマンスを上げやすい
SMSはコストパフォーマンスを上げる工夫をしやすいのもメリットです。SMS送信は1通ごとにコストがかかりますが、レスポンス率が低いやり方を排除し、売り上げにつながる方法を採用すればパフォーマンスが上がります。
SMS導入によるデメリット
ビジネスシーンにおけるSMSの活用は多くのメリットがある一方で、「文字数制限」「コスト」「法的リスク」といったデメリットが存在します。それぞれのデメリットについて、対策とともに見ていきましょう。
文字数制限による表現の制約
SMSには全角670文字(一部の機種は70文字)の文字数制限があります。詳細な説明や複雑な内容の記載が難しいため、情報を簡潔に伝える必要があります。
伝えたい要点を絞って無駄な情報を省くほか、本文だけで伝えきれない内容はURLを貼って外部サイトに誘導することで、制限内で情報を効果的に伝えられます。
コストと運用負担
SMSの送信コストは文字数によって異なり、1通あたり数円から十数円程度です。1通発信するごとに料金が発生するため、送信数が多いほどコストが増加します。SMS送信サービスを利用する場合も、1通ごとの従量課金制がとられているケースが多いです。
また、SMSの送信には、送信システムの導入費用や運用費用がかかる場合があります。さらに、送信先リストの管理や送信内容の作成、配信のスケジュール管理のための人件費が必要です。
これらのコストを削減するには、ターゲットを絞って無駄な送信を減らすことが大切です。また、一括送信機能や自動化ツールを活用することで、運用負担を軽減するのも効果的です。
法的リスクがある
SMSは特定電子メール法の対象で、送信には受信者の事前の同意が必要です。同意を得ていない場合はスパム行為とみなされて、処罰される恐れがあります。また、不適切な内容のメッセージは顧客の信頼を失うリスクがあります。
特定電子メール法の規制については次の項目で詳しく説明します。
SMSを導入する際のポイント


ここからは、実際にSMSを導入する際に重視すべきポイントを解説します。
短いメッセージで付加価値のある内容に仕上げる
SMSマーケティングではユーザー視点で付加価値のある内容を可能な限り短いメッセージで送るのが重要なポイントです。SMSはさっと見て内容をチェックし、不要な情報は排除して、有用な情報なら詳細を見るというユーザーが多くなっています。あまりにも長いSMSを送っても、最初の数十文字しか読んでもらえません。長すぎると迷惑メールだと思われてしまい、すぐに受信拒否されることもあるので気を付けましょう。
SMSはスマートフォンで受信したときにプッシュ通知を受け取る設定にしているユーザーが多いのが特徴です。SMSマーケティングではこの点に着目し、プッシュ通知でポップアップされるわずかな文で、魅力を感じ取ってもらえるようにすると効果が上がります。冒頭部分の内容を充実させて、このSMSは自分のための情報だと思ってもらうことを目指しましょう。
以前は全角70文字という文字数制限がありましたが、現在は一部の古い機種を除いて全角670文字まで送れるようになりました。しかし、むやみに文字数を増やさずに必要な情報を短くわかりやすい形でまとめ、SMSの内容だけで伝えきれない情報はリンク先に設置するのがおすすめです。
最小限の送信先に抑えて一斉送信も検討する
SMSマーケティングでは一斉送信も検討するのがおすすめのアプローチです。SMSは携帯電話番号のリストがあれば、たくさんのユーザーにまとめて送信できます。同じ内容のメッセージでも多数のユーザーに届けることで、より多くのレスポンスを受けることが可能です。一斉送信なら個別送信に比べて手間が少なくて済むため、コストパフォーマンスが高くなると期待できます。
ただし、SMSマーケティングでは送信先の数は最小限に抑えた方が良いでしょう。SMSは1通送信するごとに数円から十数円程度のコストがかかります。レスポンスが全くないユーザーに何度もSMSを送信しているとコストが増えるだけで結果に結びつきません。効果が上がりやすいユーザーを選定してターゲットにするのがSMSマーケティングをする上では重要なポイントです。
一斉送信はSMS送信サービスを利用すると効率的におこなえます。しかし、顧客リストを使ってそのまま送信するのではなく、顧客を分類して内容に応じて送信先を最小限に絞り込むことが大切です。大多数に一斉送信するのは簡単ですが、SMSマーケティングのコストパフォーマンスが下がる原因になるので気を付けましょう。
短い自社のドメイン名を短縮URLの代わりに利用する
SMSマーケティングではメッセージを短くまとめることが重要なポイントなので、URLを記載するときにも注意が必要です。URLが長いときにはURLの文字数だけで70文字以上になってしまうこともあります。文字数制限を考慮しつつ、文字数によって配信コストも変わることを考えると、少しでもURLを短くしたいと思うのではないでしょうか。その際に有用なのが短縮URLです。
短縮URLを用いれば、SMS上に記載されているURLの文字数は短くできます。ただ、文字数を減らせる反面、フィッシング詐欺ではないかと疑われるリスクが生じるので気を付けましょう。SMSによるフィッシング詐欺の被害が増えているため、ユーザーも得体の知れない短縮URLにアクセスするのはためらいます。
ユーザーからの信用を勝ち取るためには短縮URLを使わずに短い自社ドメインを利用するのがおすすめです。「〜〜〜.jp」のように偽造リスクが低い短いドメインを取得して使いましょう。SMSマーケティング用に短いドメインを取得して運用するのも賢い方法です。階層が深くならないように気を付けて運用すれば短縮URLを使わなくても短いメッセージに入れ込めます。
オプトインとオプトアウトの道筋を明確にする
SMSマーケティングでは特電法についての意識が必要です。特電法とは特定電子メール法の略称で、電子メールによる営業目的のメール送信についての規制が定められています。SMSも特電法の対象になるため、法律を遵守してSMSマーケティングをすることが求められます。
SMSマーケティングでは特電法に従ってオプトインとオプトアウトの道筋を明確にすることがポイントです。オプトインとはSMSマーケティングをする前に送信先のユーザーから事前承認を受けることを指します。オプトアウトはSMSが不要と思ったユーザーがSMSの受信をやめることです。オプトインもオプトアウトもユーザーが自分の判断で簡単にできるようにしておくのがSMSマーケティングをするときには不可欠です。
特にオプトアウトの意識がなくて問題になるケースがあるので気を付けましょう。SMSを受信しない設定をするためのURLかメールアドレスの連絡先を明示するのが典型的な方法です。ユーザーがどうやってオプトアウトしたら良いかわからないような形になっていて、SMSによるマーケティングが迷惑行為だと判断されてしまうと大きなトラブルになる可能性があります。
SMS送信サービスを活用する
SMS送信サービスはSMSマーケティングを展開する上で役に立ちます。SMSはユーザーの携帯電話番号さえわかれば個別に送信することが可能です。ただ、原則としてSMSはスマートフォンやフィーチャーフォンから送信する仕組みになっています。多数のユーザーに対して同時にSMSを送信することもできないので、マーケティング目的でSMSを配信するのは大変です。
しかし、SMS送信サービスを使えば一斉送信をすることも、パソコンからメッセージを送ることもできます。業務効率を上げることに直結するので、SMSマーケティングのコスト削減にもなるのが魅力です。また、SMS送信サービスではスケジュールしたタイミングでSMSを送信したり、顧客情報を管理して送信先を設定したりすることもできます。
SMSマーケティングの効率を上げ、コストパフォーマンスを上げるためにはSMS送信サービスを使うのがおすすめです。SMSの送信に手間をかけすぎて人件費がかさんでしまわないようにしつつ、ユーザーにタイムリーな情報を提供できるようにするためにも、SMSマーケティングをするならSMS送信サービスを活用していきましょう。
定期的に改善を目指す
マーケティングをする際にはコストと比較して十分な利益を生み出せなければ意味がありません。目的によってどのような指標で評価したら良いかは異なりますが、ビジネスでは基本的に売り上げの向上につながることが重要なポイントでしょう。
SMSマーケティングを始めたときには、効果測定をして定期的に改善のための施策を考えるのが大切です。SMSは1通ごとにコストがかかるので、少しでも配信先を減らせばコストが下がります。文字数によって1通の送信コストが変わるため、内容を吟味して短くする努力が必要なことに気づく場合もあるでしょう。
SMSマーケティングの結果を分析してみると、効果が上がっているからもっと送信先を増やした方が良いという判断になることもあります。逆に効果が出ていないのがメッセージを短くし過ぎて魅力が伝わっていないからだとわかるケースもあります。このような多角的な視点で見直しをして、より良いSMSマーケティングを目指すとコストパフォーマンスが向上していくでしょう。SMSマーケティングのツールとしてSMS送信サービスを利用すると、このような改善の施策も検討しやすくなります。
SMSの活用事例12選


ここからは、実際にSMSがビジネスシーンで活用されている事例をチェックしておきましょう。
関連リンク:ECサイトでSMSを活用するメリットは?活用シーンも併せて紹介 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
セール情報の発信
SMSマーケティングではセール情報をユーザーに配信するアプローチがよく用いられています。今日から始まるセールについて告知したり、特価品の価格について紹介したりしてプロモーションをするのが典型的です。
イベントやキャンペーンへ招待
イベントやキャンペーンについて告知したり、SMSを受信した人限定で招待したりするのもよく活用されている方法です。SMSに記載のURLからアクセスするとイベントに参加できる、キャンペーンに申し込める、というやり方が多くなっています。
予約やサービスのリマインダー
リマインダーとしてのSMSの活用もおこなわれています。来店予約やサービス申し込みなどを受け付けたときに、日時が近付いた時点でSMSを送ってリマインダーにするとユーザーから喜ばれます。
本人認証
SMSマーケティングのアプローチとして本人認証もあります。セキュリティコードをSMSで送信して二段階認証をするのがよくある方法です。ユーザーには手間になりますが、信用を勝ち取るセキュリティ面の対応策にもなります。
支払の請求や督促
SMSは支払の請求や督促に用いられることも多くなりました。借金の返済や利用料金の支払いなどで期日を忘れてしまう人もいます。SMSはリマインダーとして送ったり、支払期日に入金がなかったときに催促したりするのに有効です。
緊急時の連絡
SMSは企業からユーザーへの緊急時の連絡にも有用なツールです。システムメンテナンスの通知をするときによく活用されています。SMSはすぐに情報が伝わり、電話のように通じなくても見てもらえる点で優れている方法です。
クーポンの送付
マーケティングではクーポンの送付にSMSがよく用いられています。SMSにクーポンへのリンクを記載しておくだけで十分で、販促方法として効果的です。クーポンの取得期限や有効期限もSMSに書いておくとすぐにユーザーアクションを促せます。
アンケートの実施
SMSマーケティングではアンケートに活用する事例も増えてきました。サービスを提供した後や、商品を買ってもらった後にSMSを送信してアンケートを実施するのが典型的です。開封率の高さを生かしたマーケティングアプローチです。
電話が通じなかったときのフォロー
マーケティングには電話が頻繁に用いられていますが、通じなかった時のフォローとしてSMSが用いられています。電話で伝えたいことがあったときに留守番電話を残すと、折り返し連絡したユーザーに通話料金を負担させてしまいますが、SMSならユーザーの費用負担がないのがメリットです。
顧客フォロー
顧客フォローもSMSマーケティングにおいてよく着目されている点です。資料を提供したり、追加情報を送付したりすることでユーザーエクスペリエンスも向上するので効果的なマーケティング手法といえるでしょう。
Webサイトへのスムーズな誘導
SMSは、顧客を特定のWebサイトへ確実に誘導する手段として効果的です。特に、口頭では伝えにくいURLや、QRコードの読み取り、メールアドレスの入力といった手間を省きたい場合に有用です。顧客はSMSで送られてきたURLをタップするだけで、会員登録ページや商品紹介ページ、FAQサイトなどへスムーズにアクセスできます。これにより、情報提供の精度向上と顧客の利便性向上に繋がります。
休眠顧客の掘り起こし
長期間利用のない休眠顧客は、マーケティングにおける重要なターゲットです。SMSは携帯電話番号が変わる可能性が低いため、顧客情報が多少古くても高い確率でメッセージを届けられます。特別な割引や新サービスの案内をSMSで送信することで、顧客の再訪や再購入を促し、休眠状態からの脱却を図ることができます。低コストかつ高到達率で、顧客のLTV(Life Time Value)向上に貢献する有効な戦略と言えるでしょう。
SMS配信の法的規制と注意点
特定電子メール法は、迷惑メールの防止と電子メールの健全な利用環境の整備を目的とした法律で、主に次のような規制があります。
- 送信者名の表示
- オプトイン(事前承認)が必要
- オプトアウト(受信拒否)の手段を明記する
- 問い合わせできる連絡先の表示
メールでは送信元として名前や企業名の表示が可能ですが、SMSは原則表示できないことから本文中の記載が必要です。また、受信者への事前の承認が求められるとともに、配信停止方法や問い合わせ先に関する情報も本文中に明記しなければなりません。
オプトイン取得のベストプラクティス
SMSは特定電子メール法の対象となるため、広告や宣伝を送信する場合はオプトインの取得が必要です。
オプトインの取得には次の方法があります。
- Webサイトにチェックボックスやラジオボタンを設置する
- 登録フォームに「最新情報の送信を希望する」などの確認項目を設ける
- 個人情報の取り扱いに関する同意文の中にオプトインの取得を含める
オプトインを取得する際は、ユーザーが強制されることなく明示的に同意を示すことが大切です。法令を遵守し、信頼性を確保するための注意点は次の通りです。
- 配信目的や内容を具体的に説明しているか
- 専門用語や難しい表現は避け、わかりやすい言葉で伝えているか
- 個人情報の取り扱いについて説明しているか
- 送信される情報の種類や頻度を明記しているか
- チェックボックスに最初からチェックが入っていないか
なおオプトインの取得後は、取得した際の情報や日時などを記録しておくことも大切です。
配信停止対応の重要性
ユーザーが配信停止したいと思ったとき、停止方法がわかりにくかったり手続きが煩雑だったりすると、不信感につながります。企業の信頼を保持するためにオプトアウトの対応は次の点に注意しましょう。
- メッセージの末尾に「配信停止はこちら」などのわかりやすいリンクを設置する
- 最低限の確認で手続きが完了するようにする
- 配信停止リクエストを受けたら速やかに処理し、数日以内に完了させる
- 配信停止リストを適切に管理し、誤送信を防ぐ
SMSのマーケティングはシステム化できる!
マーケターの方ならマーケティングオートメーションについて聞いたことがあるかもしれません。SMSマーケティングはシステム化することが可能なので、マーケティングオートメーションとの相性が良いアプローチです。
マーケティングオートメーションはマーケティングを自動化するための基本的なアプローチとして導入が進められています。ユーザーの属性やセグメントなどに応じて配信する内容やSMSの送信時刻などを設定して、効果的なタイミングで効果が上がりやすいユーザーにターゲティングをすることが可能です。
また、マーケティングオートメーションではユーザーアクションと関連付けをして情報送信をすることもできます。SMSのURLからウェブサイトにアクセスしたり、商品購入をしたりしたユーザーにだけSMSを送信することも可能です。SMSでクーポンを送り、そのクーポンを使って商品購入やサービス利用をしたユーザーを特定し、次のSMSを自動送信するといったアプローチもできます。
SMSマーケティングは携帯電話番号と紐づけられているため、ユーザーとしてはダイレクトに自分だけの情報を提供してくれるものだと考えられます。マーケティングオートメーションとの連携によって履歴を自動分析し、適切な内容のSMSをベストなタイミングで送付する仕組みを整えることが可能です。
また、マーケティングオートメーションツールによってはシナリオの策定もできます。条件設定をして、ユーザーのレスポンスに応じてどのようなSMSをいつ送るかを決めることも可能です。ユーザーエクスペリエンスを向上させるアプローチとして活用が進んでいるマーケティング手法になっています。
このようなSMSマーケティングのシステム化はSMS送信サービスを活用しなければ実現できません。一斉送信ができるだけでなく、コストパフォーマンスの管理をしやすいSMS送信サービスを契約し、SMSマーケティングに活用していくのがおすすめです。
SMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
「KDDI Message Cast」は、SMS配信をサポートする高機能なサービスです。スマートフォンに直接届くSMSを活用することで高い開封率と即時性を実現し、重要な通知やキャンペーン情報を確実に届けます。
従量課金のみで配信でき、導入時の費用負担は不要。通信事業者としてのノウハウと大規模配信にも対応する安定したシステム基盤で、安心できるサービスと運用体制を提供します。
マーケティングのほか、契約手続きや入金・支払い督促の連絡、予約後のフォロー・内容確認などさまざまな用途に活用できるので、印刷代や切手代、電話代、人件費などのコストを削減したい企業様もぜひご検討ください。
まとめ
ビジネスシーンでSMSが選ばれる理由は、その確実な到達率と高い開封率にあります。携帯電話番号は変更されにくく、メールのように大量のメッセージに埋もれることなく顧客の手元に情報が届くため、その視認性は圧倒的です。これにより、重要連絡の確実な伝達から効果的なマーケティング活動まで、多岐にわたるアプローチが可能になります。
SMS送信サービスは、一斉送信や既存システムとのAPI連携によって業務を効率化し、コストを抑えつつ高い費用対効果を実現します。KDDI Message Castは国内4キャリア直収方式による安定した高到達率と、初期費用・月額費用なしの従量課金制が特長です。マーケティングを効率化し、今後のビジネスチャンスを拡大するためにぜひKDDI Message Castをご利用ください。
▼KDDI Message Cast(KDDIメッセージキャスト)詳しくはこちら
https://kddimessagecast.jp/
資料をダウンロードする(1分)




この資料でわかること
- SMSの利用実態と他コミュニケーションツールとの比較
- ビジネスシーンにおけるSMSの代表的な利用用途
- 「KDDI Message Cast」の導入事例
SMS関連の関連記事
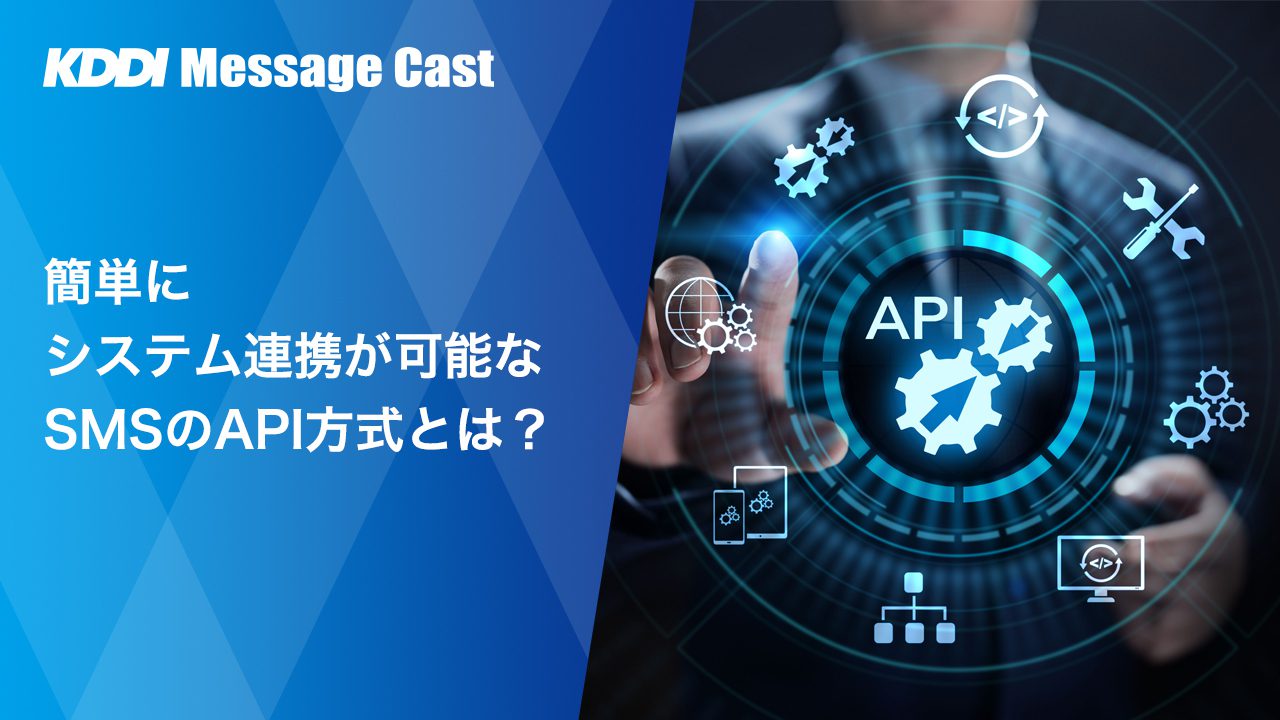
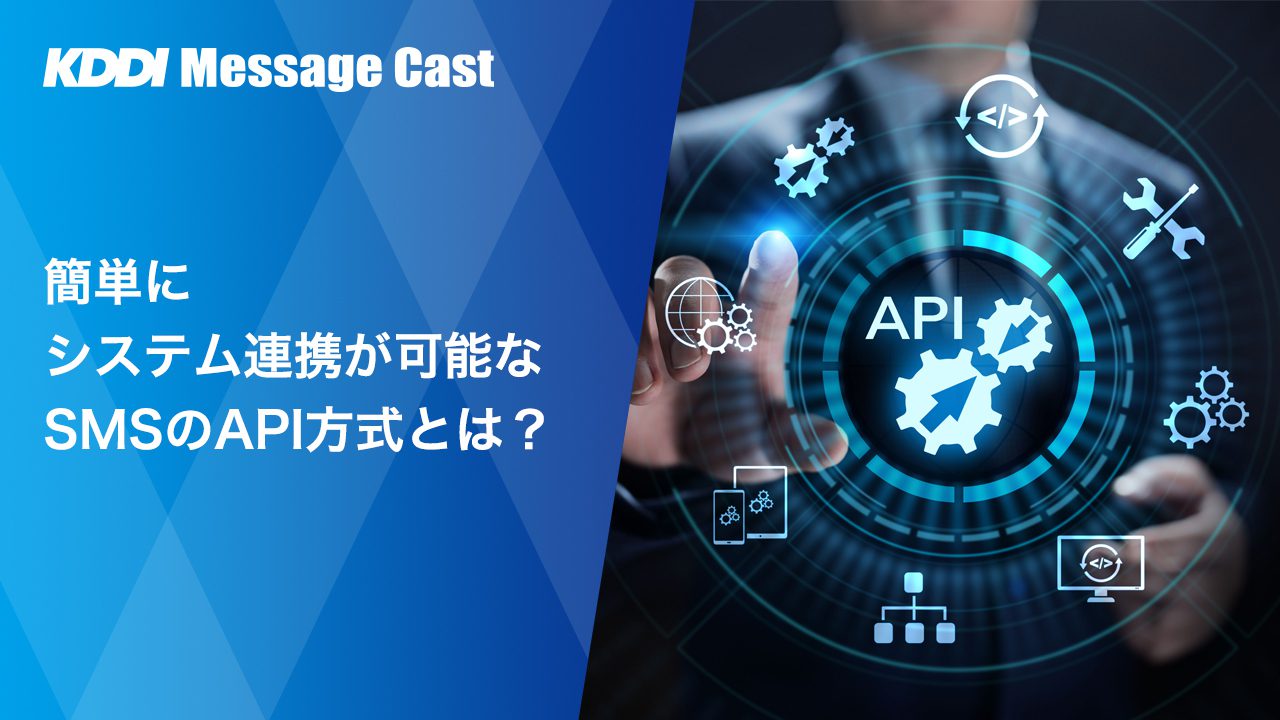
SMSのAPI連携とは?
メリットや導入手順、比較ポイントを解説!


SMSを活用したアンケート配信のメリットと活用事例を徹底解説!
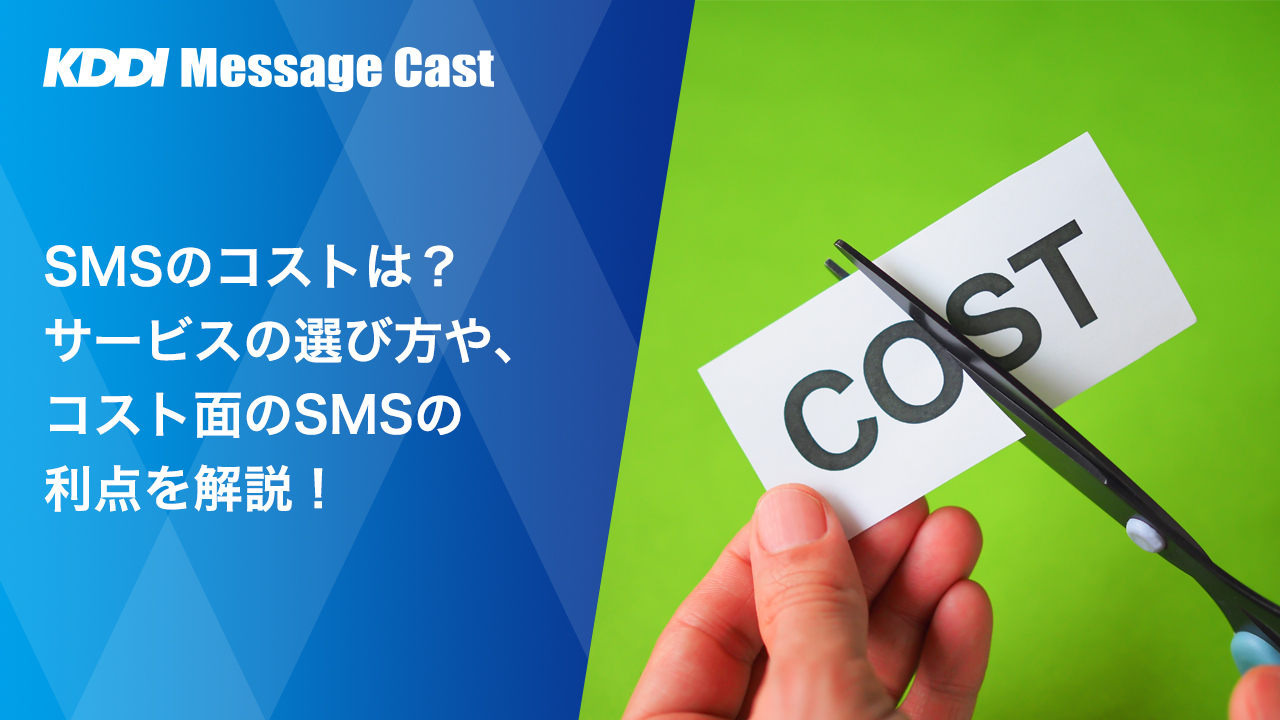
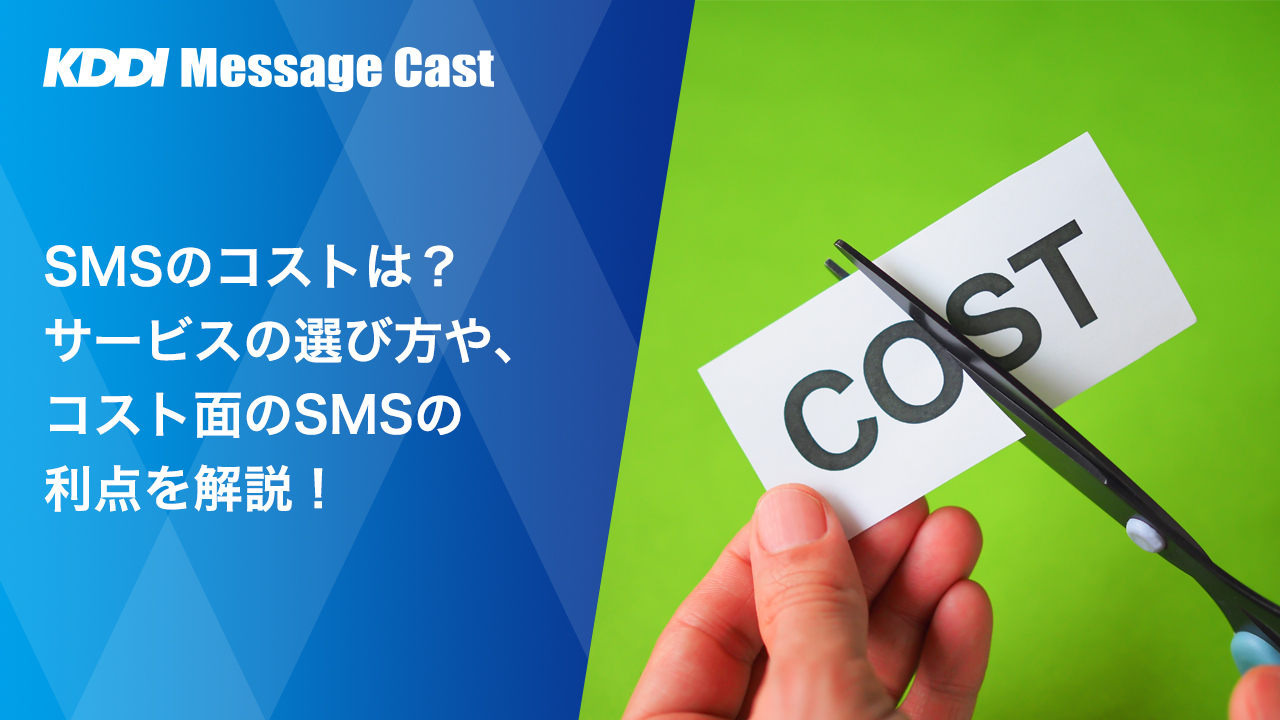
SMSのコストは?サービスの選び方や、コスト面のSMSの利点を解説!
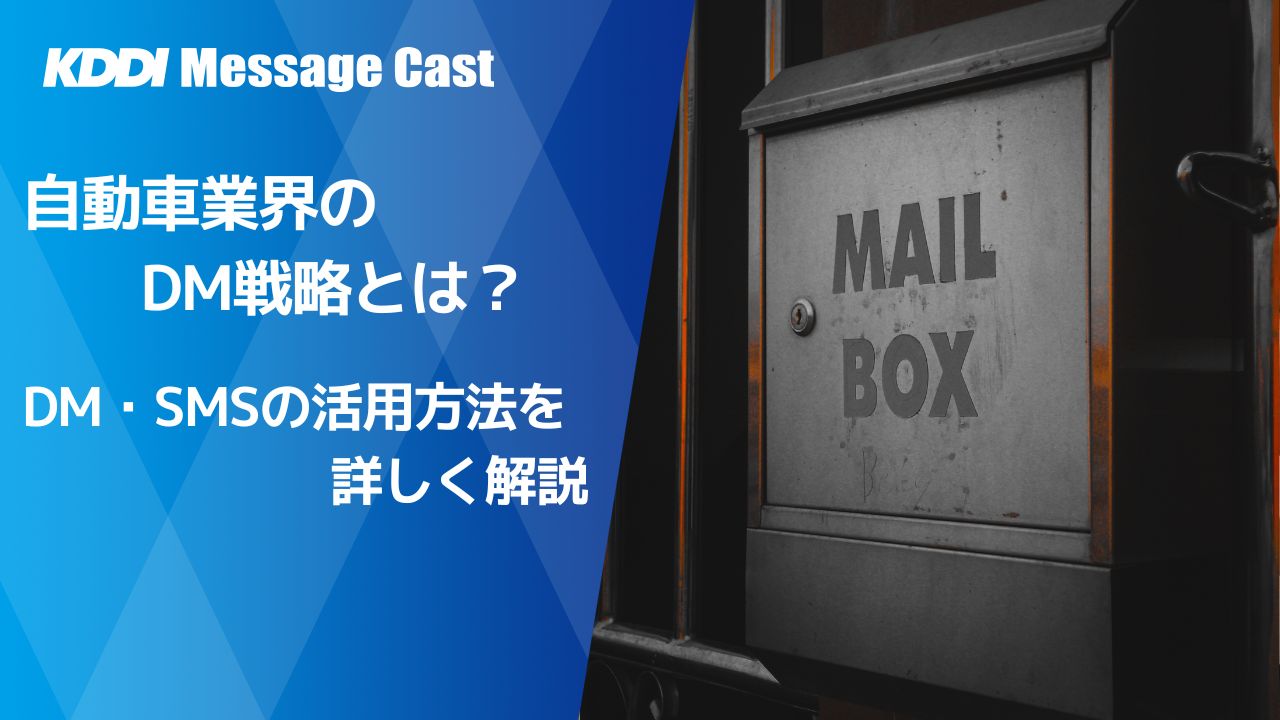
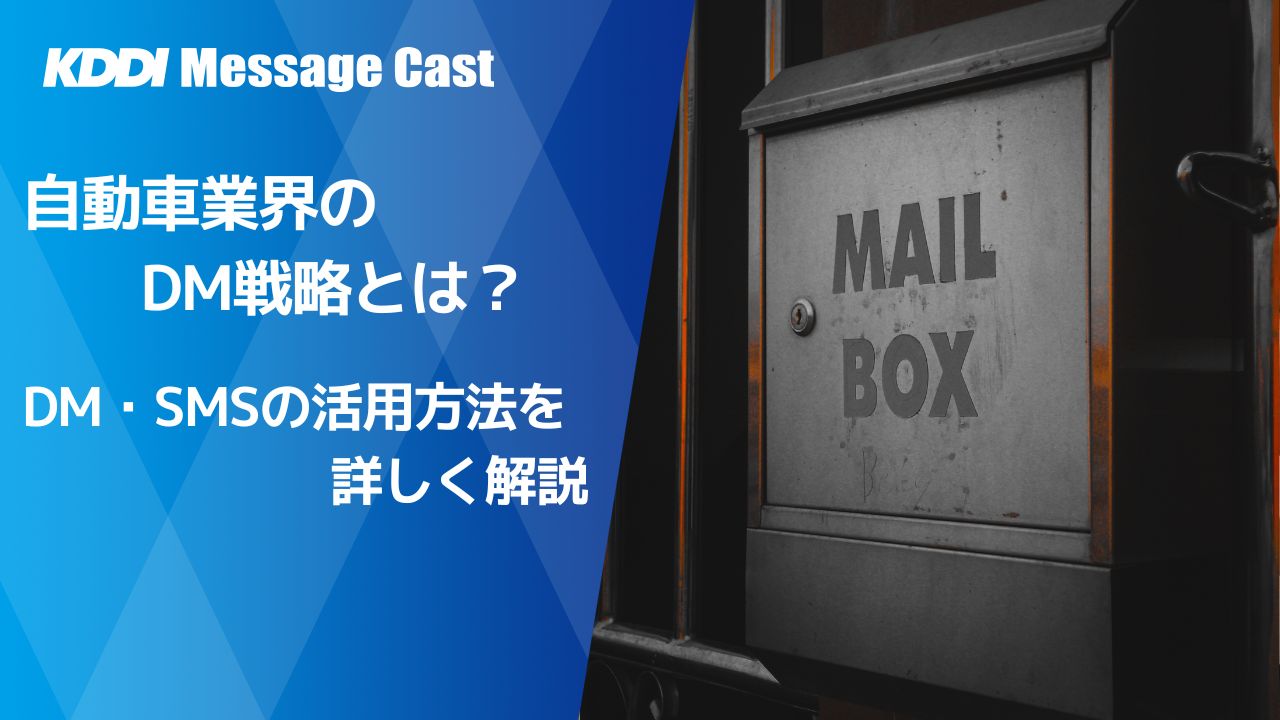
自動車業界のDM戦略とは?DM・SMSの活用方法を詳しく解説


SMSの活用事例12選!マーケティングのポイントやメリット、デメリットを徹底解説