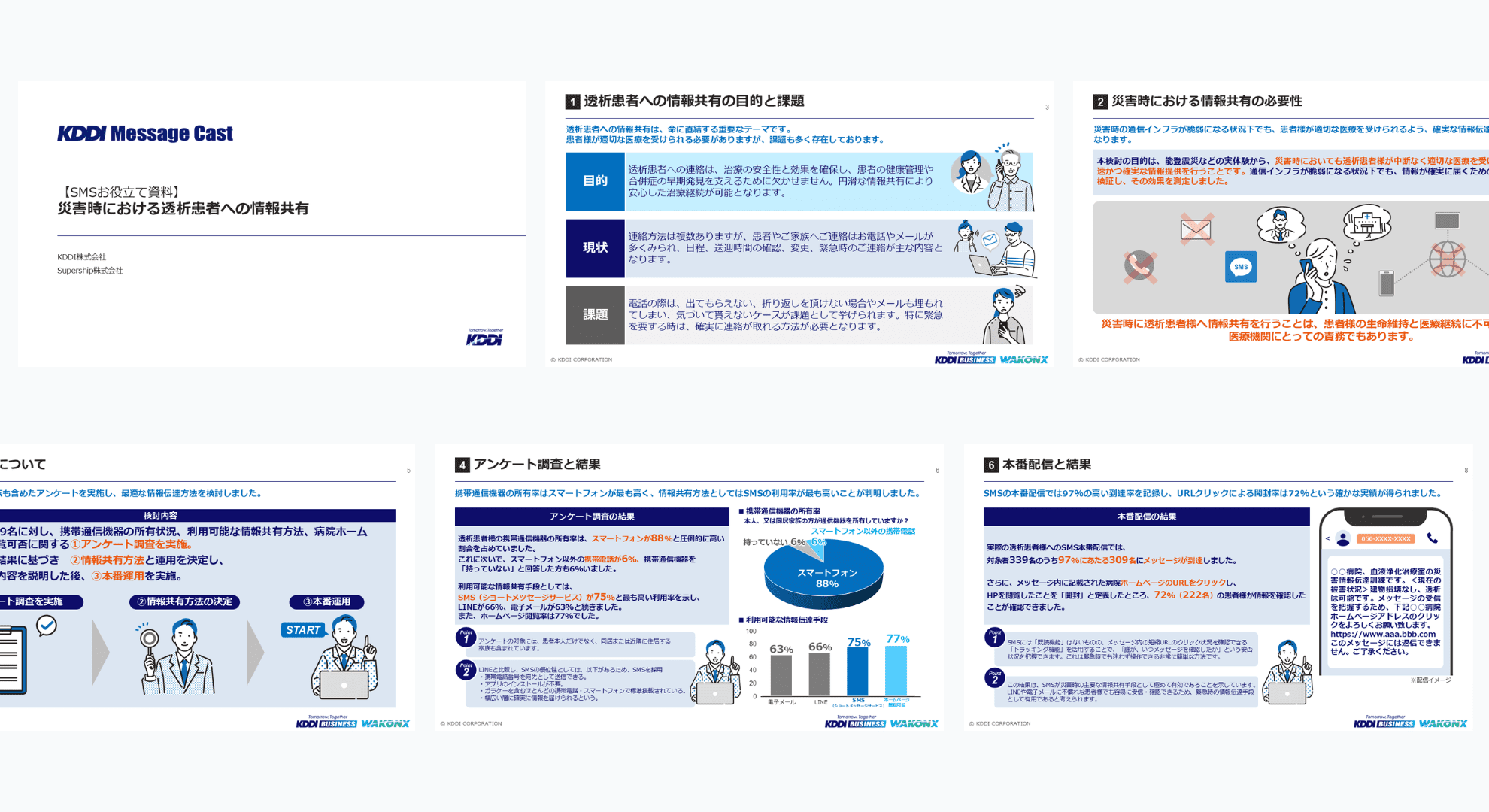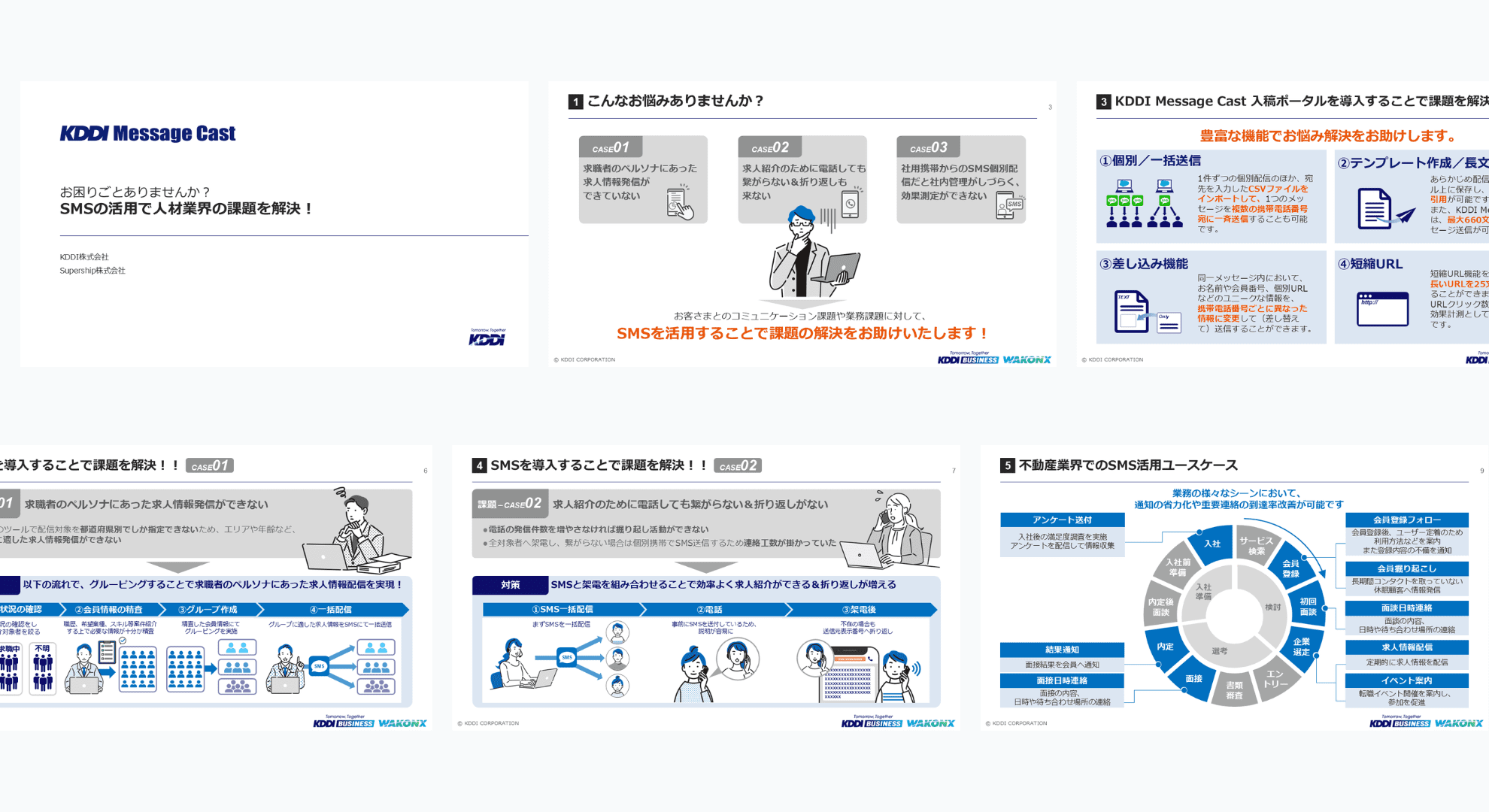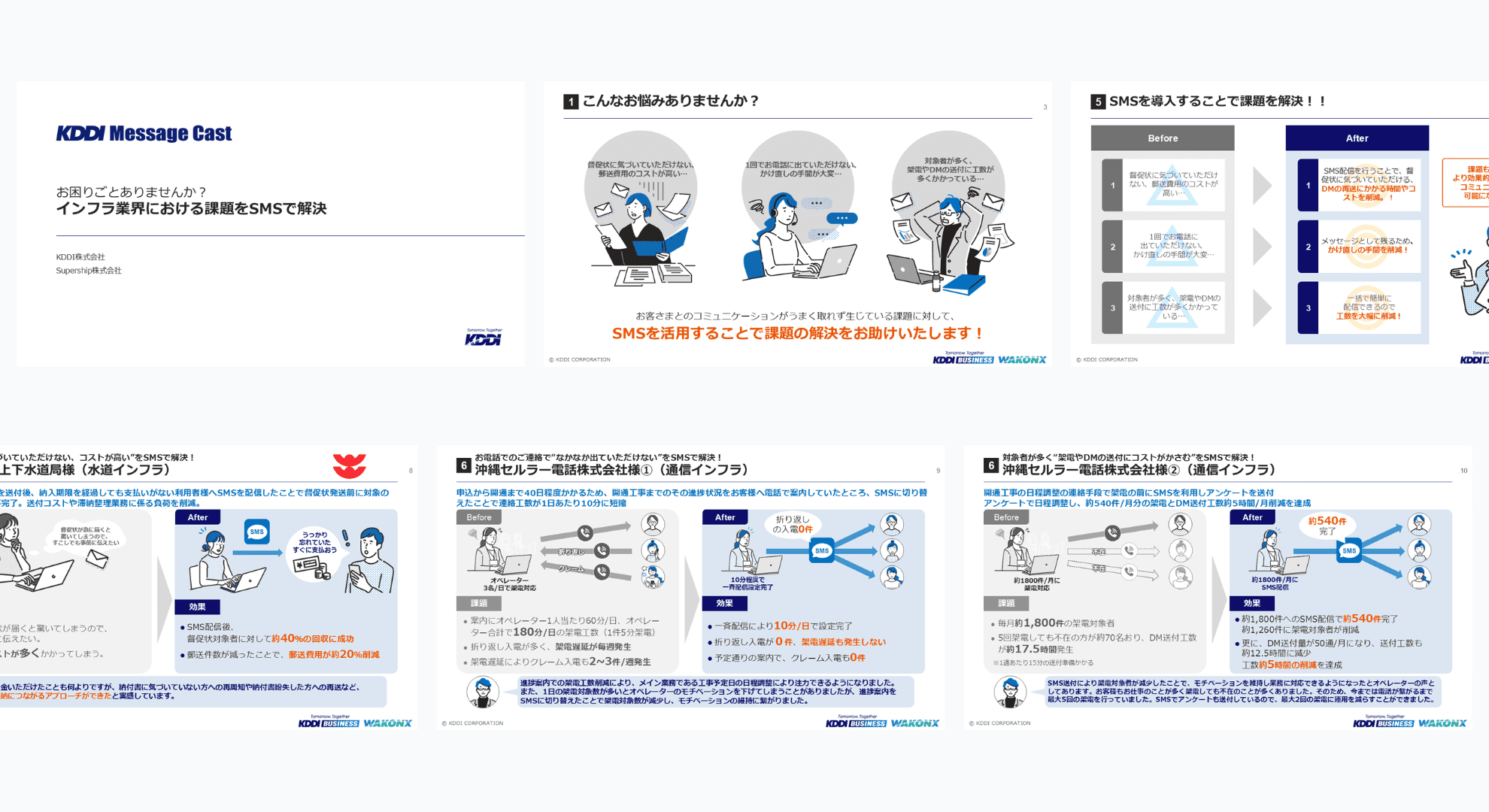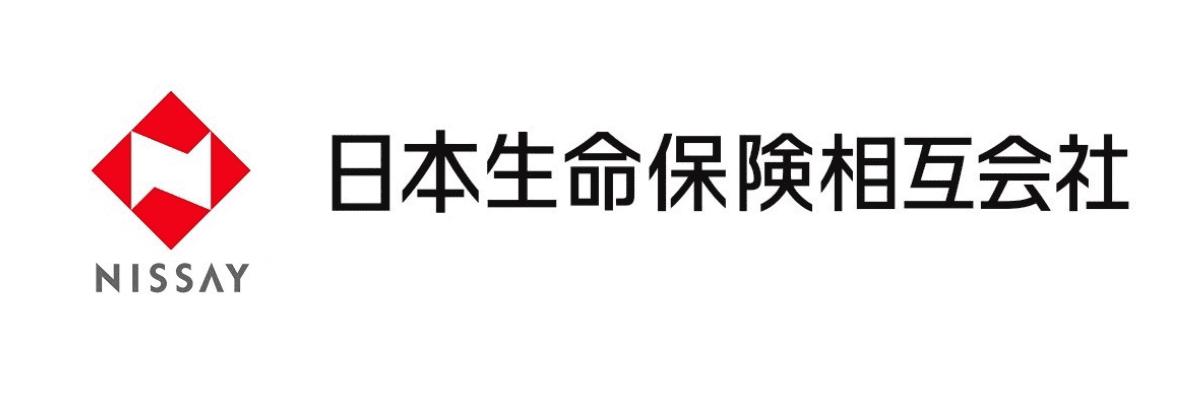医療DXとは?メリット・デメリットや事例、政府の施策を紹介

医療DXとは、単にカルテを電子化するだけにとどまりません。それは、最新のデジタル技術を活用して医療の質を向上させ、患者一人ひとりに最適な医療を提供し、医療従事者の働き方も変革する、医療業界全体の大きな取り組みです。
この記事では、医療DXの基礎知識から、導入によるメリット・デメリット、政府が進める具体的な施策、そして医療現場での活用事例まで、分かりやすく解説します。SMS活用による患者との円滑なコミュニケーション方法もご紹介します。
目次
医療DXとは?分かりやすく解説
医療の現場は、常に激しい環境変化にさらされています。この変化に対応し、デジタル技術(DX)を活用して診療や治療の質を高めていくことが不可欠です。患者や社会の多様なニーズを汲み取りながら、医療機関の経営モデルを変革していく視点も求められます。
環境の変化に対する対応
新型コロナウイルスの世界的な流行は、医療界に大きな影響を及ぼし、感染拡大への対応はもちろん、医療現場のひっ迫という深刻な事態を招きました。また、持病を持つ患者や高齢者へのケアは、より一層の配慮が求められる状況です。
こうした課題を踏まえ、新型コロナウイルスのような新たな感染症対策、進行する高齢化社会への対応、そして医療従事者の働き方改革を実現するために、業務プロセス、組織、文化、風土に至るまで、包括的な変革を行うことが医療DXとして求められています。
経営モデルの変革と課題解決
医療のデジタル化と聞いて、多くの方が電子カルテを思い浮かべるでしょう。しかし、それはデジタル化の一歩に過ぎません。医療DXは、そこからさらに進んで、蓄積されたデータの分析やAIの活用までを含みます。データへの迅速なアクセスは、過去の診療記録を参照した治療を容易にし、他の医療従事者とのスムーズな情報共有を可能にします。
電子カルテの入力作業は、慣れるまで時間がかかるという側面もあります。しかし、現場の運用効率化といった短期的な視点だけでなく、医療の質向上や経営改善といった、より大きな課題解決につながるのが医療DXの真髄です。
医療のDX実現によるメリットとは

医療DXは、医療における多様な課題の解決に貢献します。その代表的なメリットは以下の4つです。
- 業務効率化ができる
- 人的ミスや不要な検査を防ぐことができる
- 個人の健康増進が期待できる
- 医療産業・ヘルスケア産業の振興につながる
ここでは4つのメリットについて詳しく解説します。
業務効率化ができる
医療DXによって一貫性のあるシステムを構築することで、業務の効率化が実現します。データのデジタル化は情報共有を円滑にし、システムの導入はデータ入力の負担を軽減します。医療事務においては、診療報酬の請求業務の自動化や、診療報酬改定への対応負荷の軽減が可能です。また、MRIやCTなどの画像診断にAIなどのデジタル技術を取り入れることで、分析の精度と診断の効率を向上させられます。これにより、看護師や医師の業務負担が軽減され、より患者へのケアに集中できる環境が整います。
人的ミスや不要な検査を防ぐことができる
医療DXは、医療過誤のリスクを低減し、患者の医療負担を軽減することにも繋がります。システム導入によってデータの入力や転記といった作業を自動化することで、人的ミスを大幅に削減できます。他院への紹介状作成時も、正確な情報を確実に記載することが可能です。さらに、医療機関間で情報が共有されれば、専門医からの助言も得やすくなり、重複検査や不要な投薬を避けた、より的確な診断・治療が期待できます。
個人の健康増進が期待できる
医療DXの推進は、患者が自身の健康管理に主体的に取り組むことを後押しします。患者が自身の検査結果や診断内容をデータとして正確に理解し、アクセスしやすくなるからです。診療情報が医療機関の間で共有されるようになれば、どの場所で診察を受けても、情報が一元的に管理されます。将来的には、患者が自身の健康に関する詳細な情報をまとめて入手し、日々のセルフケアに活かしやすくなるでしょう。
医療産業・ヘルスケア産業の振興につながる
医療の持続的な発展には、医療産業やヘルスケア産業による技術革新や医薬品開発が欠かせません。医療DXによって現場の臨床データが整理・共有されれば、創薬研究や医療機器開発が加速します。医師主導の治験なども実施しやすくなり、保険診療の選択肢を広げる可能性も秘めています。近年、世界的に医療・ヘルスケア分野のベンチャー企業が新しい技術を生み出しており、医療DXへの貢献は、こうした産業の振興を促し、医療全体の質の向上に繋がります。
医療のDX実現によるデメリットとは
医療DXは多くのメリットをもたらす一方で、導入にはいくつかの課題、すなわちデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。
導入・運用コストとIT人材不足
医療DXを推進するためには、電子カルテやオンライン診療システムなどの導入に初期費用がかかります。また、システムの維持・管理や定期的なアップデートにも継続的な運用コストが発生します。特に、経営規模の小さい個人クリニックなどでは、このコストが大きな負担となり、導入の障壁となるケースも少なくありません。さらに、これらのシステムを適切に運用・管理できる専門的なIT人材が、多くの医療機関で不足しているという課題もあります。
情報漏洩のリスク
患者の診療情報や個人情報といった機密性の高いデータを取り扱うため、セキュリティ対策は医療DXにおける最重要課題です。オンラインでデータが連携されることにより、サイバー攻撃による情報漏洩やデータ改ざんのリスクは常に存在します。万が一、情報が外部に流出すれば、患者に多大な被害が及ぶだけでなく、医療機関としての信頼も失墜しかねません。そのため、高度なセキュリティシステムの構築と、職員のセキュリティ意識の向上が不可欠です。
医療DXにおける政府の施策
日本政府、特に厚生労働省は、医療DXを強力に推進するための指針として「医療DX令和ビジョン2030」を掲げています。このビジョンは、2030年を目標に、医療情報の活用によって国民一人ひとりがより質の高い医療を受けられる社会の実現を目指すものです。
主な施策として、全国の医療機関が患者の情報を安全に共有できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設、どこでも同じ形式で医療情報が扱えるようにするための「電子カルテ情報の標準化」、そして「診療報酬改定のDX化」などが盛り込まれています。これらの施策を通じて、政府は医療現場の効率化と医療の質向上を両輪で進めようとしています。
日本での医療DXの現状と課題
日本では医療DXの必要性が認識されつつも、いくつかの課題によってその進展が阻まれている状況があります。ここでは、現状と課題を4つの観点から解説します。
- 高齢化に伴う人材不足
- 電子カルテの導入
- 医療データ形式の標準化が必要
- オンライン常時接続が進んでいない
高齢化に伴う人材不足
日本では少子高齢化が進み、医療現場は深刻な人材不足に直面しています。医療DXを推進するためには、ITスキルを持つ優秀なDX人材が不可欠ですが、多くの医療機関では、まずは医師や看護師といった医療専門職の確保が最優先課題となっています。特に、診療報酬が主な収入源である保険診療機関では、高給なDX人材を確保するための財源的余裕が乏しいのが実情です。
電子カルテの導入
電子カルテの導入は、医療DXの基盤として進められています。紙のカルテをデジタル化し、医療機関間での情報共有を目指す取り組みは、徐々に広がっています。しかし、システムの導入と運用には高額なコストがかかるため、大病院では導入が進む一方で、個人経営のクリニックなどでは導入が難しいという格差が生じています。
医療データ形式の標準化が必要
医療DXを全国的に推進するためには、医療データの形式を標準化することが不可欠です。各医療機関が異なる規格のデジタルデータを使用していては、情報を円滑に共有・活用できません。国際的な標準規格である「HL7 FHIR」の導入が進められていますが、現場レベルでの普及には至っておらず、医療機関のデータを真に連携させるには、まだ時間がかかる状況です。
オンライン常時接続が進んでいない
リアルタイムでのデータ共有には、医療情報システムが常にインターネットに接続されている必要があります。しかし、個人情報や医療情報が漏洩するリスクを懸念し、意図的にインターネットから切り離して運用している医療機関も少なくありません。医療DXのメリットを最大限に活かすためには、情報を安全に守りながら、いつでもオンラインでつながるような仕組みを早く整えることが重要です。
長時間労働
医師や看護師をはじめとする医療従事者の長時間労働は、日本の医療が抱える根深い課題です。DXによる業務効率化は、この問題の解決策として大いに期待されています。しかし、新しいシステムの導入期には、操作の習熟や運用ルールの変更などで、かえって現場の負担が増加することもあります。多忙を極める医療現場において、DX推進のための時間や人的リソースをいかに捻出するかが、大きな課題となっています。
医療業界でDXが進みにくい理由
医療DXが進みにくい背景には、これまで挙げたIT人材の不足やインフラの問題に加え、医療業界特有の事情も存在します。多くの医療機関は地域医療を担う安定した存在であり、民間企業のような激しい市場競争にさらされることが少ないため、DXによる競争力強化へのインセンティブが働きにくい側面があります。経営が成り立っている限りは、コストや手間をかけてまで現状の運用を変える必要性を感じにくい、という保守的な考え方が、DX推進の足かせとなっている場合があります。
DX導入のための課題、メリットや導入しないことによるデメリット・リスクなどを徹底解説 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
医療のDXのトレンド傾向
新型コロナウイルスの影響を契機に、遠隔診療(オンライン診療)が医療DXの大きなトレンドとして注目されています。患者は自宅にいながら診察を受けられるため、院内感染のリスクを避けられます。
また、高齢や病気で通院自体が大きな負担となる患者にとっても、遠隔診療は有効な選択肢です。地方在住者が都市部の専門医の診察を受けることも可能になり、医療の地域格差是正にも繋がることが期待されています。オンライン接続のための準備は必要ですが、患者の移動に伴う身体的な負担が減るため、スタッフの介助業務などの負担軽減にも繋がります。
医療現場でDXを推進する方法
医療現場でDXを効果的に進めるには、システムやツールの導入といった技術的な基盤整備が不可欠です。しかし、それ以上に重要なのが、導入したツールを全スタッフが使いこなせるようにするための教育体制を整えることです。例えば、電子カルテの入力を補助する音声入力システムの活用や、院内の情報共有を円滑にするスマートデバイスの導入などが考えられます。
新しい作業に慣れるまでは一時的に負担が増えるかもしれませんが、一度定着すれば、業務効率は飛躍的に向上し、より質の高い医療を提供するという大きなメリットに繋がります。
DX戦略とは?立て方や推進プロセス、成功のポイントもご紹介 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
DXソリューションとは 成功事例や導入方法、選定のポイントなどを徹底解説 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」 – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
医療現場でのSMSの活用事例
医療現場では、SMS(ショートメッセージサービス)や、その進化版であるRCS(リッチコミュニケーションサービス)を活用して、患者様との連絡をもっとスムーズにできます。
- 予約変更の電話対応を減らし、スタッフの負担を軽減
予約忘れ防止のSMSは非常に効果的です。さらに進化版のRCSなら、メッセージに「予約を変更する」「キャンセルする」といった返信用のボタンを付けることができます。これにより、患者様はメッセージ上で簡単に手続きができ、医院の電話応対の時間を減らすことにも繋がります。 - 写真付きの案内で、分かりやすく
文章だけでは伝わりにくい定期健診のご案内も、写真付きならもっと分かりやすくなります。例えば、人間ドックの案内を郵送ハガキの代わりにRCSで送れば、コストを抑えつつ、複数の検査コースの違いを写真でスライドして見せることも可能です。検査前の注意事項などをイラストで送る、といった活用もできます。 - 「いつもの病院」だと分かる安心感
RCSなら、メッセージに病院のロゴマークを表示できます。患者様は「いつもの病院からの連絡だ」と一目でわかり、フィッシングSMSと間違えることなく、安心してメッセージを開封できます。保険証の確認や事前問診のURLなど、大切な連絡も確実に届けられます。
関連リンク:SMS(ショートメッセージ)送信サービスの医療業界での活用ケース – SMS送信サービス「KDDIメッセージキャスト」
RCSとは?SMSとの違い、メリット、ビジネス活用事例まで徹底解説
法人向けSMS送信サービスなら「KDDI Message Cast」
患者とのコミュニケーション改善には、法人向けSMS送信サービス「KDDI Message Cast」が最適です。
- 初期費用・月額費用0円。まずは無料で効果を実感
KDDI Message Castは、初期費用や月額固定費が不要な従量課金制です。さらに、無料トライアルも実施中。管理画面の使いやすさや患者様の反応を、コストをかけずにご確認いただけます。 - 写真やボタンで、もっと伝わる。「RCS」に対応
文章だけのSMSだけでなく、写真やボタン付きのメッセージ(RCS)も送れます。病院のロゴも表示できるので、患者様も安心です。RCSが利用できない方(古い機種など)には、自動的に通常のSMSを配信する機能もあるため、大切な連絡が届かない心配もありません。 - 医療機関に不可欠なセキュリティ
電話番号の持ち主が変わった場合に配信を停止する「誤配信防止オプション」もご用意。個人情報を扱う医療機関様にも安心してご利用いただける機能を提供します。長文を配信する場合、複数通に分かれるSMSよりもRCSの方がコストを抑えられるケースもあり、費用対効果にも優れています。
医療DXの第一歩は、患者様との確実な連絡手段を確保することから。ぜひ「KDDI Message Cast」をご検討ください。
まとめ
本記事では、医療DXについて、その基本的な考え方からメリット・デメリット、政府の施策に至るまで幅広く解説しました。
医療DXは、単なるデジタル化に留まらず、ビッグデータの活用や診断精度の向上など、医療全体の未来を形作る大きな可能性を秘めています。導入には課題もありますが、乗り越えることで業務効率化、医療の質の向上に繋がります。
いきなり大規模なシステムを導入するのは難しくても、まずは確実性と信頼性の高いSMS/RCSを活用した患者とのコミュニケーション改善から始めるのが、医療DXの現実的な第一歩と言えるでしょう。
KDDI Message Castなら、初期費用・月額費用は不要で、無料トライアルも可能です。この機会に、ぜひその効果を実感し、貴院のDX推進にお役立てください。
DX関連の関連記事

物流DXの課題解決にSMS活用が必須!物流業界のDX推進事例と成功ポイント
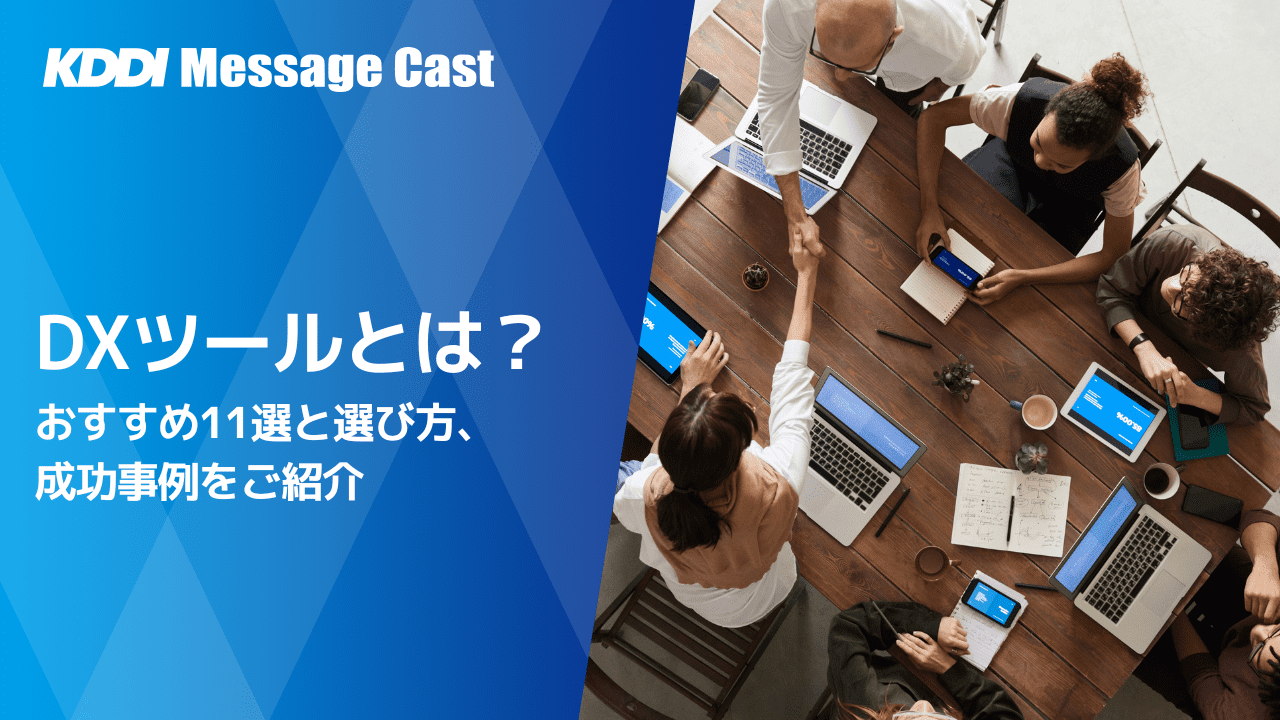
【2025年版】DXツールとは?おすすめ11選と選び方、成功事例をご紹介

エネルギー業界のDX「5つのD」とは?インフラ分野のSMS活用事例とコスト削減効果
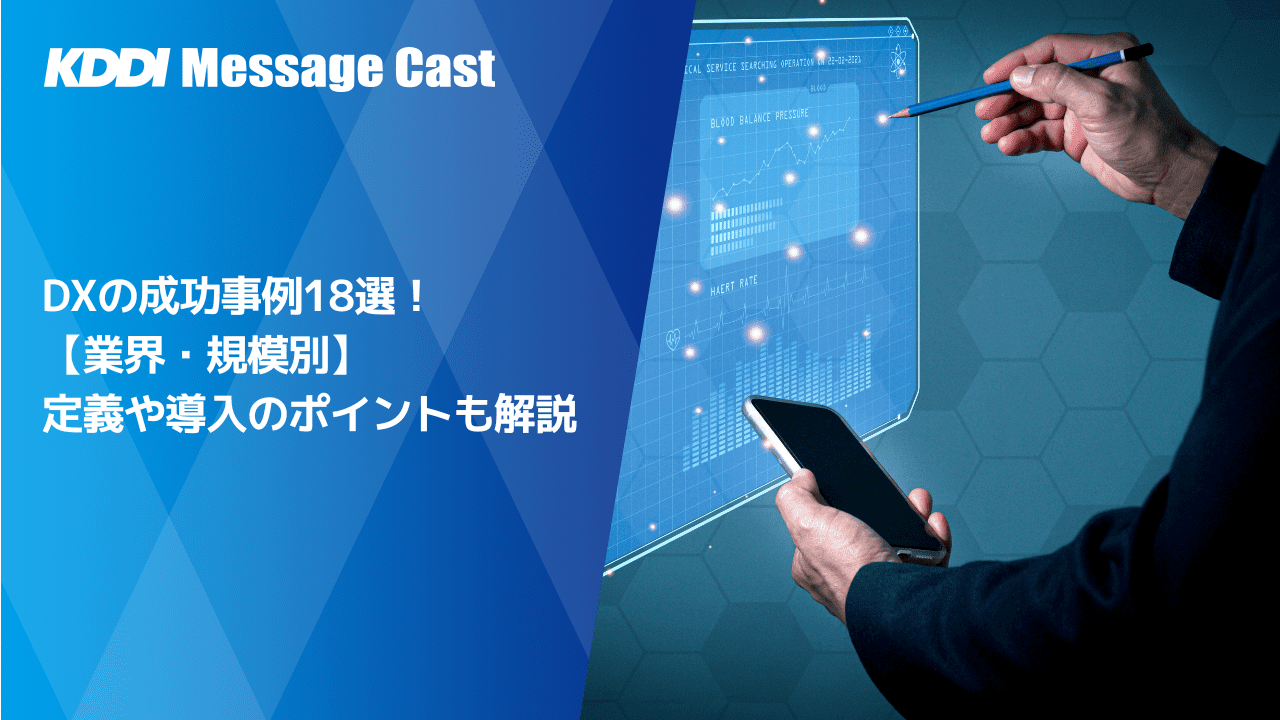
DXの成功事例18選!【業界・規模別】定義や導入のポイントも解説

建設DXとは?導入メリットや課題は?DX化の進め方や事例を紹介